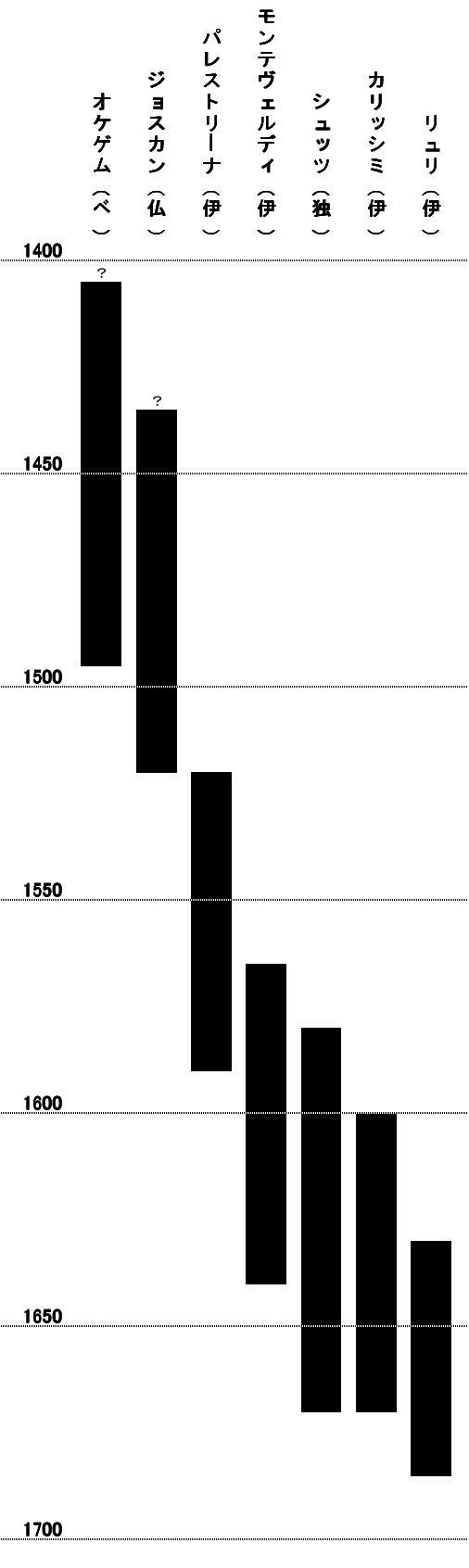|
�ʤ�������������Ǥ������ޤ������������䤷�Ƥ����ޤ��Τǡ����ڤ��ߤˡ���

����Ǥ�����Ǥ���
|
�������ѤΥڡ���
���Υڡ��������̤˰������Ƥ�;ʬ����ʬ����������Ƥ��ޤ��ޤ��Τǡ�
�������������ϡ����Υ�����Ѥ���������
����������Τ�Ź�ˤ��֤��Ƥ���ޤ��Τǡ���θ�ʤ��������դ����������ޤ���
�������ܼ�����html�ǡ���pdf��
��������ʸ����html������pdf��
�������ʤ�����������ˤĤ���
��������������åפ��Ƥ����ޤ���
|
������ͥ�����
- ��ϥ�ͥ�����������
��Joannes Ockeghem��1410?-1497���֥르���˥����[���ߤΥ٥륮���ն�]��
�������ե��ɥ���ɤδ���Ū¸��
�������͡��������ڥǥ����֥�ϥͥ������������
���ܤǤϡ������������(1416ǯ��)�����Τ���(1467ǯ��)�ʤɡ���Į�����������ؤ��������������Ϥ������������ޤ���
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
��ϥ�ͥ����������ࡡ��ߥ������å�����������顦�ɥߥˢ�ι�
�ֽ��ޡ���ϻ������ͥ����ڤΥ�������åפ�ȤäƤ����Τϡ��ե��ɥ������ʺ�������٥륮��������̥ե�˽пȤ�
�췲�β��ڲȤ����Ǥ������������������ѤΥ�ͥ����礭����㤹��Ȥ����Ǥ��ơ����ڤΥ�ͥ��ϥ���ץ����̤Υե��ɥ���ɤ�
���ڲȤˤ�äƥ�ɤ���Ƥ����櫓�Ǥ���¿�������ʲȤΤʤ��Ǥ⡢����������Ⱦ�˸���ơ��ե��ɥ���ɤδ��ä��ᡢ
�������äΥݥ�ե��ˡ���ˡ�γ���˹�������ϥ�ͥ����������ब���פǤ�������ά��
 �ʥ���ƥå� A340A �ĥ�������
�ʥ���ƥå� A340A �ĥ�������
|
���ƥѡ��Ȥϡ����줾���ȼ�����Χ���¤��Ф��ơ�̵�¤�ήư���Ƥ����ޤ���
�����⡢�����˺�ꤢ�����Ƥ����ϡ���ˡ��ν��¤�ʹ���Τ����ޤ���
�Ĥޤꡢ�ġ����Ȥ��̩�٤Τ�����̩�ʲ��ڤ���夲�Ƥ椯��
----���줳���ե��ɥ벻�ڤ���ħ�Ǥ��ꡢ�ޤ��������ऽ�οͤ���ħ�Ǥ⤢�ä��ΤǤ�����
�إߥ������å������������顦�ɥߥˡ�
��ˮ�����ߥ��ʡ֤��ϼ�ΤϤ�����ʤ��
�����ꡧMissa ecce ancilla domini��Pro Cantione Antiqua��Collegium Aureum
�����Ǹ���harmonia mundi


- ���祹���ǡ��ץ�
��Josquin Des presz��1440?-1521���ե��
�������ե��ɥ���ɤν��פ�¸��
�������͡��������ڥǥ����֥��祹���ǡ��ץ��
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
���祹���ǡ��ץ졡��ߥ����ѥ��������ι�
�֥��祹���ǡ��ץ�ϡ��������������θ���ơ��������������齽ϻ�����ν�Ƭ�ˤ����Ƴ����������ե��ɥ���ɤ�
��ɽŪ�ʺ�ʲȤǤ������Υ쥪�ʥ�ɡ�������������Ȥۤ�Ʊ����˳������Ƥ��ޤ������쥪�ʥ�ɤ����Ѥξ�Dz̤������Ż���
���祹����ϡ����ڤξ�Dz̤�������ɾ�����Ƥ�������Ǥ��礦����
�֥Х��å����ڡסʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�������ߥ����ѥ������������ƥȥ����㥢�������ޥꥢ���Τ褦�ʶ���������ʤˤ����ơ�
���ڤˤ������ͥå����ͼ���ĺ���ˤ����ä��Ȥߤʤ��Ƥ褤����
�إ�ƥȥ�������¯�����
�����ꡧMotets et Chansons��THE HILLIARD ENSEMBLE
��������Σ��ʡ֥��٥ޥꥢ�ס�Ave Maria��

�إߥ����Х�����������߸˳�ǧ��
��The Art of the Netherlands
��EARLY MUSIC CONSRT OF LONDON directed by DAVID MUNROW��
���������ࡢ���祹����������¾��������ͥ��ˤ�����ե��ɥ���ɤζʽ���
- ���������ˡ��ԥ���륤�����������ѥ쥹�ȥ��
��Giovanni Pierluigi da Palestrina��1525?-1594�������ꥢ��
�����������ꥢ�Υ�ͥ����ڲȡȶ��ڤ����
�������͡��������ڥǥ����֥���Х�ˡ������ѥ쥹�ȥ�ʡ�
WikiPedia�֥��������ˡ������ѥ쥹�ȥ�ʡפι������
�֥��������ˡ��ԥ���륤�����������ѥ쥹�ȥ�ʤϡ������ꥢ����ͥ�����β��ڲȤǤ��롣���̤ˡ֥ѥ쥹�ȥ�ʡפȸƤФ�뤬�����������ˤ�̾���ԥ���륤�����������ѥ쥹�ȥ�ʤϸ�ҤΤ褦�����ϤǤ��롣���ȥ�å��ν����ʤ�¿���Ĥ��ֶ��ڤ���פȤ⤤���롣
������
�����ꥢ����ͥ��λ��������ڤϥե��ɥ뤬�濴�Ǥ��ꡢ��������ģ�β�����ˤ�ե��ɥ�β��ڲȤ��Ȥ������֤Ǥ��ä������ѥ쥹�ȥ�ʤϥ����ꥢ�Ͳ��ڲȤȤ����礭��̾����������
���ʤ��Ȥ�100�ʾ�Υߥ��ʡ�250�ʾ�Υ�ƥȤ���Ȥ����¿���ζ��ڤ��ʤ�����Ǥ��ֶ��ĥޥ�����륹�Υߥ��ʡ��������ɽ��Ȥ���Ƥ��롣����ά��
���ʤ˸����롢�缡�ʹԤ���ΤȤ������ǡ�ʿ������̩�ʹ羧�ͼ��ϥѥ쥹�ȥ���ͼ��ȾΤ���Ƥ��롣�ѥ쥹�ȥ�ʼ��Ȥϲ����������䤷���櫓�ǤϤʤ����������ͼ���18�����Υեå����ζ��ܰ��踷���а�ˡ�����ϤǤ���Ȥ���Ƥ��롣��
�ض��ĥޥ�����륹�Υߥ���
�����ꡧMISSA PAPAE MARCELLI 8 MOTETTEN
�����Ǹ���ARCHIV


�إ��å쥰�ꡧ�ߥ�����
�����ꡧALLEGRI MISERERE
�����̡�1. ALLEGRI: MISERERE��2. MUNDY: VOX PATRIS CAELESTIS
�����̡�PALESTRINA: MISSA PAPAE MARCELLI�ʶ��ĥޥ�����륹�Υߥ���


�����Х��å�����
- ���饦�ǥ��������������ˡ�����ȥ˥������ƥ�����ǥ�
��Claudio Giovanni Antonio Monteverdi��1567-1643�������ꥢ��
�������Х��å����ڥ�δ��ä��Ω
�������͡��������ڥǥ����֥��饦�ǥ��������ƥ�����ǥ���
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
���饦�ǥ��������ƥ�����ǥ����㰦���������ˤʤ������ͤ��ޢ�ι�
�֥��ƥ�����ǥ��ϡ���ͥ����ڤ���Х��å����ڤؤΰܤ��Ѥ�λ����ˤ��ġ������ꥢ�κ�ʲȤǤ�������ά��
�������Ϻ�ϡ���ͥ��դ��Υޥɥꥬ���줬��ȯ���ˤʤäƤ��ޤ��������Τʤ��˸��դȲ��ڤȤΰ��פ����е���ۤɡ�
����ݥ�ե��ˡ��θ�����Ω�ĥޥɥꥬ����Ϸ�Ū�ʡָ��פβ��ڤ����Ƥ�����ʤ��ʤ�ޤ���������ά��
���������Ȭ���Υޥɥꥬ����ʽ�����Ǥ��Ƥ��ޤ����������ˤϥ�ͥ�����Х��å��ؤβ��ڤΰܤ��Ѥ�����꤬üŪ��
���ᤵ��Ƥ��ơ������ؤ�̣�֤�����Τ�����ޤ�����
�֥Х��å����ڡסʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
��1607ǯ�ˤϥޥ�ȥ�����Į�ǡ����饦�ǥ��������ƥ�����ǥ���ʤΥ��ڥ��㥪��ե���������餵�졢
���ڥ�Ȥ����ڼ�γ�Ω�˷���Ū�ʹ���Ϥ�������
���θ�ΥХ��å����β��ڤϡ�������Ĥ���ݴ�ڲ��ڤȷ�ڤȤ��濴��Ÿ�����Ƥ椯���Ȥˤʤä�������ά��
�����ε���ڥ�դ��ι����ˤ⤫����餺�����ƥ�����ǥ��β��ڤζ��������Ϥˤϡ�����������ò����ۤ��ʤ��ä���
�˸�����С���ڤȤ���ɬ�פʼ�ˡ�ϡ����٤Ƥ������������Ƥ����ɾ�����롣��
�إ��ꥢ��ʡ�������L'Arianna SV291�פΤ���ͣ�츽¸����
�����ꡧLamento d'Arianna
��ˮ�������ꥢ��ʤ�ò��
�����Ǹ���harmonia mundi


�إ���ե�����������L'Orfeo SV318�פ��
�����ꡧL'ORFEO
�����Ǹ���TELEFUNKEN


������ޥꥢ�Τ�����ղݡ��ʡ�����ޥꥢ��ͼ�٤ε���٤Ȥ��
�����ꡧVESPRO DELLA BEATA VERGINE
�����Ǹ���ERATO


- �ϥ����ҡ�����å�
��Heinrich Schütz��1585-1672���ɥ��ġ�
�������ХåϤ���100ǯ���Υɥ��ġ��Х��å����ڤ�����
�������͡��������ڥǥ����֥ϥ���ҡ�����åġ�
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�ϥ����ҡ�����åġ��㥯�ꥹ�ޥ�������ȥꥪ��ι�
���㥯�ꥹ�ޥ�������ȥꥪ���Ǥϡ�����̾���ΤȤ��ꡢ���ꥹ�ȹ��¤Τ��ꤵ�ޤ�����θ��դˤ�äƲΤ��Ƥ��ޤ���
�������ڤȤϤ������ʤˤ����ꥹ�ޥ��������ɤ������粻�ڤĤ��Ǥ�äƤ����褦�ʡ�����ʳڤ����ˤߤ������ʤǤ���
���������ڤ�����ʤ�Ρ��ऺ��������ΤȻפ�����Ǥ���ä�������ˤϡ����Ҥ����ɤ��Υ���åĤζʤ�İ����������������
�������ڤ������˿ʹ�Ū�ʡ��ʹ֤������뤳�Ȥκ����ˤ��ޤä����ڤǤ��뤫�Ȥ������Ȥ�ǧ�����Ƥ�������������ΤȻפ��ޤ�����
�ϥ����ҡ�����åġ���ॸ������å��塦�������������������ι�
���㥨������������������Ȥϡ㤪��Ȥ������ȤǤ����������ॸ������å��������Ĥޤ�㲻�ڤˤ�롦������Ȥ������ƻ줬�Ĥ��ޤ����顢�����Ѳ��ڡ�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ�������ά��
�����Ф��Х���åĤζ������Ӥ������ڤ���������Ť��ˤ����褦�˴����뤳�Ȥ�����ޤ���������Ǥ���ʹ������ä����δ�ư�Τդ����Ϥޤ����Ȥ��褦�⤢��ޤ����������ԻĤʲ��ڤ��Ȼפ��ޤ�����
�إޥ�������� SWV 479��
�����ꡧMATTHAUS PASSION
�����Ǹ���EMI��TELDIC��


�إ��ꥹ�ޥ�������ȥꥪ��
�����ꡧChristmas Story
����Ͽ�ʡ�
����A�� �����ʡ�Historia der freudenreichen Geburt Jesu Christi SWV 435a��
�������������ʥ����������ꥹ�Ȥδ�Ф������¤�ʪ���
����B�� ��Magnificat anima mea Dominum SWV 468�١ʥޥ˥ե������ȡ�
�����Ǹ���ORFEO


�إॸ������å��塦�������������������
�����ꡧMusikalische Exequien SWV 279-281
�إॸ������å��塦��������������������136��
�����ꡧMusikalische Exequien Psalm 136
�����Ǹ���EMI��TELDIC��


- ���㥳�⡦����å���
��Giacomo Carissimi��1605-1674�������ꥢ��
�������ǽ�Υ���ȥꥪ��ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥��㥳�⡦����å��ߡ�
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
���㥳�⡦����å��ߡ��㥤���ե���ι�
���㥤���ե����ϡ�����������о줹������������ե���ʪ��Ǥ������羡����Ϳ���Ʋ�����С���ʬ���Ȥ˵���Ĥ�������
�ǽ�˷ޤ���Ԥ����Ȥ��Ƥ������ޤ��פ����äơ����μ��ˤ�äƾ�������ޤ����Ȥ�������̿�Τ�������Ȥ����ΤǤ��礦����
�ब�郎�Ȥˤ��ɤ��夤���Ȥ��ˡ���Ƥ�ޤ��ˤ��ɤ�ǤƤ����Τϡ��ǰ���̼�Ǥ��ä��ΤǤ���
�����Ȥ���«�ˤ�äơ����ʤ�̼�����Ȥ��Ƥ������뤳�Ȥˤʤä������ե���ò����̼���ᤷ�ߡ�——�����������Ū��ʪ�줬��
���Υɥ�ޤȤ��ơ��Τ��Ƥ����ޤ����Ȥ��ˡ��Ǹ��̼�λ����͡��Υ����饹�ϡ�̾��Ȥ����Τ��Ƥ����ΤǤ�����
�֥Х��å����ڡסʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥���å��ߤΥ���ȥꥪ�ϵ�������Ȥ�졢�ƥΡ����Ⱦ��ˤ����������濴�ˡ����줾����������ƥ��DzΤäƤ椯��
�����ǤϤ�Ϥ���ڤη�Ū��Фϲä���줺����������ղ�����DzΤ��뤿�ᡢ�����äƲ��ڤ��ʤ���ľ��Ū�Ƕ����ʤΤǤ��롣
������
�����������ò���ι羧�Ϥޤ��˰����Ǥ��äơ��Զ��²���ⲿ����Ѥߤ����ͤƤ椯ñ��ʹ����ˤ⤫����餺��
�դ��������Ϥ��ä�ʹ���Ԥˤ��ޤäƤ��롣�������Ѥ����Ƥ��벻�������ʤ���ñ��Ǥ�������ˡ������ϤϤʤ����ޤ�ΤǤ��롣��
��HP����������������סʤ��礦�ӡˡ������Ǹ�ˤʤä�����������ˤʤ뤳�ȡ�
��JEPHTE ET TROIS MOTETS��
��ˮ�ꡧ�����ե�
����Ͽ�ʡ�
����A�̡�JEPHTE
����B�̡�MOTET ��O QUAM PULCHRA ES��
����������MOTET ��O VULNERA DOLORIS��
����������MOTET ��SALVE, SALVE, PURLLULE��



- ������Хƥ����ȡ�����
��Jean-Baptiste [de] Lully��1632-1687�������ꥢ��
�����������ꥢ�пȤΥե���Х��å������ڥ��ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥�����Хƥ����ȡ������
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
����Хƥ����ȡ����ꡡ�㥢��ߡ��ɢ�ι�
�֥���Хƥ����ȡ�����ϡ������ꥢ�����ޤ졢�ե�dz����������ڲȤǤ�������ά��
�����ޤ��γںͤ���ӿͤ餵�̼Ҹ�κ�ǽ��ȯ�����ơ������ޤ��Τ��������۲��륤�������ΰ��ܤ�
������褦�ˤʤ�ޤ���������ά�˥����ꥢ�ͤǤ���ʤ��顢�ե���Х��å������ڥ�δ��ä��ۤ�������
���Ȥˤ�ʤä��ΤǤ���
�����Τ褦�ʽ��פʺ�ʲȤǤ���ˤ⤫����餺���쥳���ɡ����������˼����줿�쥳���ɤο���
�����Ƹ¤��Ƥ��ޤ�������ϡ�����ά�˥Х��å������ڥ����˺������뤳�Ȥ��ۤȤ���Բ�ǽ�ˤ�����
�Ȥ������Ȥξڤ��ˤۤ��ʤ�ޤ�����ά��
�������Υ��ڥ鳦�˷��פ��Ƥ��������ȥ顼�Ȳμ�β�����ɤ�����ˤ�ߤ��������뤫——
����Բ�ǽ�Τ����Ĥ�β���Ȥ����Ʋ�褷�ʤ��¤ꡢ�Х��å������ڥ��錄����������������ɾ������
�Ȥ������ȤϤ��ꤨ�ʤ��ΤǤ�����
�֥Х��å����ڡסʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥���λ��45ǯ�ˤ���ե�β��ڰ����Ȥϡ֥��꤬�ޤ������Ƥ��ơ��礭�����ǡ�����ά�˳���˵������ʤ��褦�ʻؼ���
Ϳ���Ƥ��������ˡ�����Υ��ڥ�����ȤΤ���ͤӤȤϡ����Τ����Τ褦��ɽ���ϡ��⤦�����Ǥϸ����ʤ��ʤä��ȴ����뤳�Ȥ�
�������פȵ����Ƥ��롣
18�����ν�Ƭ�ˤϡ����Ǥ˥�����դ������ϼ���줫���Ƥ����ΤǤ��롣����20�����˥���β��ڤ�˺�Ѥ��������ɤ�����Ƥ��ޤä�
���Ȥϡ�����ʤ����ͳ�Ϥ���櫓����������������ե���ڤδ��ä���ꤷ������θ��ӤޤǤ�̵�뤹�뤳�ȤϤǤ��ʤ�����
��Grands Motets��Dies Irae ��Miserere��
����Ͽ�ʡ�
�������ܤ�����סʡ�Dies Irae�ס��ǥ������������
�����֤�������ߤ��ޤ��סʡ�Miserere�ס��ߥ��졼���
�����Ǹ���harmonia mundi


- ���륫������������
��Arcangelo Corelli��1653-1713�������ꥢ��
�������Х��������Τι��ղ��ڤκ�ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥��륫�������������
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
���륫�����������ꡡ�㥯�ꥹ�ޥ������������Ȣ�ι�
�֥��륫������������ϡ���Ȭ������Ⱦ�Υ���������ڤ�Ÿ���ˡ����פʹ���Ϥ�����
�����ꥢ�κ�ʲȤǤ�������ά��Ű�줷�����������Ȥꡢ�ɤκ��ʤ���̩�Ƕ��Ƥ���Ѥ�ߤ��Ƥ��ޤ�������ά��
���ε��ʤ��롢��Ĵ�⤤���ڤ��ʤ���ޤ��������ȼ��Τ�ΤǤ�������ά��
������ϻ�ι��ն��նʡʻ��켷����ǯ���ǡˤϡ����������ռԤ��礭�ʹ��ե��롼�פȤ�����Ȥ�����
�Х��å�Ū���������ˤ�äơ����夲���Ƥ��ޤ�������ά��
���ʽ���Ȥ���ͭ̾�ʤ�Τ���Ȭ�֤ǡ�����ά�ˤޤ����Ҳ�Ū�ʥ��ꥹ�ޥ��ε�ʬ�ˤߤ����¶ʤǤ�����
���륫�����������ꡡ��顦�ե��ꥢ��ι�
���ȥ顦�ե��ꥢ���Ȥϡ����ڥ���ͳ����㲻��Χ�ǡ��������������Ū�ʥѥå��������äơ�
�����˿��������������ղä��Ƥ椯�ʼ�Ǥ������κ��ʤˤ��줿�������ϡ���Ȭ�����Υ������������ɤ�
�˱ɤ�ȿ�Ǥ����Τ����ꡢ�����⥳������ͭ�γ�Ĵ�ι⤵��¢���Ƥ��ޤ�����������������նʤΤʤ��Ǥ⡢
�Ȥ��˵��������٤�̾�ʤȤ��ơ����ҤȤ���٤�ʹ���Ƥ���������ΤǤ�����
�֥Х��å����ڡסʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֤�����ξ��ˤ��Ƥ⡢�����ν����ϡ������դ������դȤ�����ˤ����äƤ��ꡢ
�����դ��Ȥ��˺�Ω�ä�Ķ��Ū�ʱ��յ������ᤵ���褦�ʤ��ȤϤʤ���
�ޤ�����⡢�����դ������դ˶�������ʬ���졢�������դ�������������������Ū�˱������ꡢ
ȿ�������ꤹ������Ѥ����Ƥ��롣
������
�⡼�ĥ�������١��ȡ��������ξ��ȤϤ����äƥ�����������ռԤȥ������ռԤ����Ƹ����ռԤΣ��ͤ��դ�����
��Festliche Barockmusik��
����Ͽ�ʡ������ꥹ�ޥ���������������
�������ʹ��ն��ն� ����6 ��8�� ��ûĴ "Fatto per La notte di Natale"��
�����Ǹ���DECCA

�ع��ն��նʽ� Op.6��
���ꡧ12 CONCERTI GROSSI OP.6
����Ͽ�ʡ�
�������ն��ն� ����6 ��1�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��2�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��3�� ��ûĴ
�������ն��ն� ����6 ��4�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��5�� �ѥ�ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��6�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��7�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��8�� ��ûĴ
�������������ꥹ�ޥ�������������(fetto per la notte di Natale)��
�������ն��ն� ����6 ��9�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��10�� ��ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��11�� �ѥ�ĹĴ
�������ն��ն� ����6 ��12�� ��ĹĴ
�����ա�I MUSICI�ʥ����ॸ����
�����Ǹ���PHILIPS
��12 CONCERTI GROSSI OP.6��
����Ͽ�ʡ�
�������顦�ե��ꥢ�סʸ��ꡧ��Variationen über »La Follia« op.5, Nr.12�ס�
������Sonate in F-dur�ס�ˮ��������
�����ۤ�
�����ռԡ�
����Frans Brüggen�ʥХ��å��ե롼�ȡ�
����Anner Bylsma�ʥ�������
����Gustav Leonhardt�ʥ�����Х������륬���
�����Ǹ���PHILIPS
�إ�����������ʥ���Ⅱ��
����Ͽ�ʡ�
�����֥�����������ʥ�������5����4�֡���ĹĴ��
�����֥�����������ʥ�������5����10�֡���ĹĴ��
�����֥�����������ʥ�������5����5�֡���ûĴ��
�����֥�����������ʥ�������5����11�֡���ĹĴ��
�����֥�����������ʥ�������5����6�֡���ĹĴ��
�����֥�����������ʥ�������5����12�֡���ûĴ ���顦�ե��ꥢ���
�����ռԡ�
�������ɥ�����ȡ���륯���ʥ�����������
�����������㲻��
�����楲�åȡ��ɥ�ե她�ʥ�����Х������륬���
�������������ȥޥ����ʥ�������
�����Ǹ���ARCHIV
- �ߥ������ꥷ�㡼�롦�ɥ������
��Michel-Richard Delalande��1657-1726���ե��
�������ե���Х��å����ڤκ�ʲȤǡ��ե����륬�˥���
�������͡��������ڥǥ����֥ߥ������ꥷ�㡼�롦�ɥ���ɡ�
�������ڥǥ����֥ߥ������ꥷ�㡼�롦�ɥ���ɡפι������
�֥ߥ������ꥷ�㡼�롦�ɥ���ɤϥե���Х��å����ڤκ�ʲȤǡ��ե����륬�˥��ȡ�������Хƥ����ȡ��������ե������ץ����Ʊ����ˡ����۲��ε���ڲȤȤ��Ƴ������륤14���β����β��ڶ��դ�̳�ᡢ1714ǯ������ǯ�ޤDz�������Ʋ�γ�Ĺ��̳�����
��rééditions��
����Ͽ�ʡ�
������HYMNE «Sacris Solemniis»�ס�M.R.Delalande��
������GRAND MOTET «Nolite me considerare»�ס�Pierre Robert��
������TE DEUM�ס�Eustache du Caurroy��
�����Ǹ���ERATO
- ���������ˡ��Хåƥ��������������åƥ�
��Giovanni Battista Viotti��1755-1824�������ꥢ��
����������Х��������ˡ����
�������͡��������ڥǥ����֥��������ˡ��Хåƥ��������������åƥ���
�������ڥǥ����֥���Х�ˡ��Хåƥ��������������åƥ��פι������
�֥�����������ռԤȤ��ƤΥ������åƥ��αƶ��Ϥ��礭�����ԥ����롦�����ɤ�ԥ����롦�Х��������ɥ�ա��������ĥ�������ϸ����̾�ʶ��դȤʤä��ˤ��礭�ʱƶ���Ϳ�������Ӥ��顢�������åƥ���19�����Υե���������������ɤ����ߤ���ȸƤФ�롣�ޤ����ݤ�����ԥե��ȥ���ơʥȥ�����ȡˤ˽�����Ϳ�������ߤΰ���Ū�ʵݤη�����夲��������ά��
�������åƥ��κǤ���פʺ��ʤϡ������١��ȡ��������˱ƶ���Ϳ�����Ȥ���롢29�ʤ�������������������ն�����������22�֥�ûĴ����23�֥�ĹĴ�ʤɤ�ͭ̾�Ǥ��뤬���Ȥ�櫓��22�֥�ûĴ�ϡ����γ������ղȤ��濴�ˡ������˱����Ƥ�������٤��ˤ�ƹ⤤���������åƥ��κ��ʤ�¿���ϥ�������������˳�������21�ʤ������븹�ڻͽ��նʤǤϥϥ��ɥ�γ����ֶѹդμ�줿�����פ��礭��̵�뤵�졢��1��������������դ����ܤ�̤����Ƥ��롣����ڶʤ˱�������ϡ�2��Υ����������ȥХ��ʤɡ��������Ū���Ȥ߹�碌���Ѥ��Ƥ��롣��
�������ڥǥ����֥�����������ն���22�� (�������åƥ�)�פι�����ѡ�
�֥֥顼�ॹ��襢�ҥ�Ϥ��ζʤλ����ԤǤ��롣
�֥顼�ॹ���Ȥϥ١��ȡ�������Υ��������Ȥ��⤳�ζʤߡ�
�襢�ҥ�Υ�������������Υԥ��ΤDz������դ�ڤ���Ǥϡ������٤˴��㤷�Ƥ����Ȥ�����
�ޤ��١��ȡ��������������åƥ��κ��ʤϤ褯�ΤäƤ��ꡢ�ƶ���������Ȥ����Ƥ��롣
�إ�����������ն���22�֡���Concherto No.22��
����Ͽ�ʡ�
�����֥�����������ն���22�֡ʥХ�������������ȥ�ˡ�
�����֥�����������ն���22�֡ʥԥ��Ρ��Х�������ڹ����ġ�
�����Ǹ���turnabout

- �إ����ѡ�����
��Henry Purcell��1659-1695�������ꥹ��
�����������ꥹ����ɽ����Х��å����ڲ�
�������͡��������ڥǥ����֥إ����ѡ������
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�إ����ѡ����롡������ɡ��ȥ����˥�����ι�
�ֽ���������Ⱦ�Υ����ꥹ�ϡ���������ζ������ˤ�äƷݽѳ�ư�����������������Ȥ�줿���ᡢ���ڤ��Կ������Ƥ��ޤ�����
���������θ�β������Ť����äơ��ե�䥤���ꥢ�β��ڤ��Ѷ�Ū�˼������褦�Ȥ�����̡������ꥹ�Х��å����ڤ��椿����
Ÿ�����뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ���
��������ɽŪ�ʲ��ڲȤϡ��鷺������ϻ�Ф����¤����إ����ѡ�����Ǥ�������ϡ����׳ڴ�Τ���β��ڡ����ڹ��նʡ�������ʬ���
�����줿���ʤ�Ĥ��Ƥ��ޤ�������Τ�������Ӳ��ڡ��Ȥ�櫓���ڥ����ά�ˤˤ����Ƹ�����̾��Ĥ��Ż���Ϥ����ޤ�������
��Ode à Sainte Cécile��
����Ͽ�ʡ�
�����������ꥢ�ν����Τ���Υ�����
�����֤�Ǥ������������������ꥢ��(Hail, bright Cecilia!)��Z.328(1692)
���������������ƥʡ���Alfred Deller
�����Ǹ���harmonia mundi
- ����ɥ졦����ץ�
��André Campra��1660-1744���ե��
�������ե����Х��å����ڤν����ʤȲη����ɽ�����ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥���ɥ졦����ץ��
�������ڥǥ����֥���ɥ졦����ץ�פι������
�֥���ɥ졦����ץ�ϥե�κ�ʲȡ��ش��ԡ������ԡ�
������Хƥ����ȡ�������������ե���åס���⡼���������ˤ����롣
�ե����Х��å����ڤν����ʤȲη����ɽ�����ʲȤȤ���̾�⤤��
�Ȥ�櫓�Ի�ԤΤ���Υߥ��ʡ��ϡ���������κ��ʤ��¤�Ω��¸�ߤǤ��롣��
�ػ�ԤΤ���Υߥ��� Requiem��
�����ꡧMESSE DES MORTS (Requiem)
�����Ǹ���ERATO
��UNBEKANNTE CONSTBARKEITEN��(B��)
����Ͽ�ʡ�Nativitas Domini Nostri Jesu Christi
�����Ǹ���schwann MUSICA MUNDI
- �ޥ륫��ȥ�̡������ѥ�ƥ���
��Marc-Antoine Charpentier��1643?-1704���ե��
�������ե�������Х��å����ڤ���ɽ�����ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥ޥ륫��ȥ�̡������ѥ�ƥ�����
�������ڥǥ����֥ޥ륫��ȥ�̡������ѥ�ƥ����פι������
�֥ޥ륫��ȥ�̡������ѥ�ƥ����ϥե�������Х��å����ڤ���ɽ�����ʲȡ�¿��Ȥ��������줿��ʲȤǤ��ꡢ��˽����ʤ����פʡ�������Хƥ����ȡ�������Ʊ����ͤǤ��롣�ե����ȤۤȤ�ɴ�Ϣ�������������ˤʤäƽ���������ǧ�����줿���ᡢ��������������������¿����
����ά��1672ǯ�����ˡ�������Хƥ����ȡ���������¤ˤʤä���ꥨ����ȶ��ϴط������롣����ά�ˤ��λ����κǤ�ͭ̾�ʺ��ʤ����ԥơ��ǥ��� ��ĹĴ�����������ᄎŷ�ߥ��� Mass "Assumpta Est Maria" ���Ǥ��롣
�����ʤΤۤ��ˡ����治�ڤ䡢ʬ�ष�ˤ������ʤ��������롣�����ξ��ʤϡ������Υ����ꥢ�Υ������˻��ơ���Ĥ���Ĥ����ڥѡ��Ȥȴ�ڤΤ���˺�ʤ���Ƥ��ꡢ�ڼ��̾�Τ�����ФۤȤ�ɶ����������롣�����ѥ�ƥ������ȤϤ����ξ��ʤ�֥����롦������air sérieux �����ͤʥ��ꥢ�ˡפȤ���air à boire�פȸƤ���������ϥե��ʤ�Ф����Ǥ��������������ꥢ��ʤ�Х����������Τ����٤���������
������
�ԥơ��ǥ��� ��ĹĴ�դ����նʤϡ��衼���å�����Ϣ���signature tune�Ȥ��Ƥ�����ͭ̾�ǡ��������ե���ϡ���ˡ����˥塼���䡼�������Ȥ�桼�����������ξ�����ƥ��Ȥγ��ϥơ��ޤˤ�Ȥ��Ƥ��롣��
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�ޥ륫��ȥ�̡������ѥ�ƥ������㿿����Υߥ���ι�
�֥����ѥ�ƥ����Ȥ�����ʲȤϡ��Ϥ����Ȥ�֤��ƥ����ꥢ��α�ؤ����ΤǤ���������å����Υ���ȥꥪ��ʹ���ƴ�ư�Τ��ޤ��Ȥˤʤ뤳�Ȥ��ᡢ���ڲȤˤʤäƤ��ޤä��ͤǤ���
���⤹��Ф��ޤ��̿ͤΤ���β��ڤ˷��������Υ륤��ī�Υե���ں��ʤΤʤ��ǡ������ѥ�ƥ����κ��ʤ������Ҥ���İ���ˤफ�äƳ����줿�����᤹�Τ⡢�����ѥ�ƥ������οͤ��������ȴط�������Τ��⤷��ޤ���
�إơ��ǥ����
�����ꡧTE DEVM
�����Ǹ���ERATO
�������ᄎŷ�ߥ��ʡ�
�����ꡧMissa Assumpta est Maria
�����Ǹ���ERATO
��UNBEKANNTE COSTBARKEITEN����A�̡�
�����ꡧMesse de Minuit pour Noël
��ˮ�ꡧ���º�����Υߥ��ʡʿ�����Υߥ��ʡ�
�����Ǹ���schwann MUSICA MUNDI
�أ��ĤΥ���������Τ���Υ������
�����ꡧConcert pour quatre parties de violes
�����Ǹ���MUSICA MUNDI
��MEISTERWERKE DES FRANZÖSISCHEN BAROCK��
����Ͽ�ʡ����ĤΥ���������Τ���Υ�����
���������� (Concert pour quatre parties de violes)
�����Ǹ���MUSICA MUNDI
- ����ߥʡ��֥顼��
��Carmina Burana��
������19�����ϤẢ�˥ɥ��������ΥХ������ȯ�����줿���ν�
�������͡��������ڥǥ����֥���ߥʡ��֥顼�ʡ�
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�ֽ��������Τ������齽�����������ˤ����ơ��衼���åѤˤϡ���ά�˽����ˤ��֤�ơ����͡�ȿ����Ū�ʿ����
��Ĥˤ����ä�����ƥꤿ������ά�ˤ���ƥ��ˤ�äư����䶵����Ƚ�����ä��ζʤϡ������㥫��ߥʡ��֥顼�ʡ�
�Ȥ���̾���βζʽ��ǻĤ���Ƥ��ޤ�������ά��
�����ˤϡ�����ƻ���佡����Χ����ʤ������Ȥ����ʹִ��𤬤ߤ�졢�������ͤο���ˤ��̤��벿��Τ���ʹ���Ȥ��ޤ���
����ꤹ�ޤ����ȥ���������ߥ�ͥ����ζʤȤϤ����ä���������硹�οʹ����Ȥ����櫓�Ǥ��͡���
�إ���ߥʡ��֥顼�ʡ�
�����ꡧ��ORFF: CARMINA BURANA��
����Ͽ�ʡ�
����FORTUNA IMPERATRIX MUNDI (FORTUNE, EMPRESS OF THE WORLD)
����Ⅰ PRIMO VERE (IN SPRINGTIME)
����Ⅱ IN TABERNA (IN THE TAVERN)
����Ⅲ COUR D'AMOUR (THE COURT OF LOVE)
���ش��ԡ�LEOPOLD STOKOWSKI
�����Ǹ���FULL DIMENSIONAL SOUND
��CARMINA BURANA volume1 VERSION ORIGINALE & INTEGRALE��
����Ͽ�ʡ�
����CARMINA GULATORUM ET POTATORUM
����CARMINA AMORIS INFELICIS
���ش��ԡ�RENÉ CLEMENGIC
�����Ǹ���harmonia mundi
- �ե������ץ��
��François Couperin��1668-1733���ե��
�������ХåϤ��¤ֶ��륬��ȥϡ��ץ������ɤ�̾�ꡢ����Э�ե�ΥХåϭ�
�������͡��������ڥǥ����֥ե������ץ���
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�ե������ץ�㶵�趵��Τ���Υ��륬�ߥ���ι�
�֥ե�Υ����ץ��Ȥϡ��ХåϲȤ�Ʊ�͡��塹�����줿���ڲȤ����ߤ����Ƥ������Ȥ�ͭ̾�ʲ����Ǥ�������ά��
���ե�郎���륬��Τ���˺�ʤ������ʤǤϡ���ʤΥ��륬��Τ���Υߥ������趵��Τ���Υߥ�������ƻ���Τ���Υߥ�����
�����פǤ���������⡢���ȥ�å��Υߥ�ŵ��륬��ˤ�äƲڡ������������Ȥ����տޤ����ʤ���Ƥ��ޤ�����
���β�������Ʃ���ʹ����ʤɤ����ǥɥ��ġ����륬�ڤȤϤҤ�̣�����ä���Τᤷ�Ƥ���ΤǤ�����
�ե������ץ�����Τ��������ʥ���֥���ʽ����ˢ�ι�
�����۲��륤�������ϥե������ץ��γںͤ�ߤȤᡢ�鷺���Ф�����������Ʋ�Ĥ����륬���ռԤ�Ǥ̿���Ƥ��ޤ�������ά��
�֥����륵����ΥХ�פǤϤ���ޤ�����ī��̣�ζ��Ϥ˥����ץ��β��ں��ʤ�����櫓�Ǥ�������ά��
�������Τ����������ϡ�����ά�����ͤ��ӵ����������������Ϥʤ䤫���������Τʤ��ˡ���뤻�ʤ��Τ��Ƥ����ޤ���
��LA REINE DES COEURS��
����Ͽ�ʡ�
������8�ȶ� ��9�ʼ�Ͽ��
�����������
�������ѥå����ꥢ
�������ۤ�
������14�ȶ� ��7�ʼ�Ͽ��
����������������
����������������ξ�
�������ۤ�
������21�ȶ� ��5�ʼ�Ͽ��
�����Ǹ���argo
��MASTER WORKS FOR ORGAN VOLUME4��
����Ͽ�ʡ�
����[François Couperin]
������ƻ���Τ���Υߥ���(MESSE POUR LES CONVENTS)
����[Louis Couperin](F.Couperin����)
����ALLEMANDE in G minor
����SARABANDE en canon in D minor
����CHACONNE in G minor
�����Ǹ���nonesuch
�إ����ץ����ʽ���
����Ͽ�ʡ�
�������껿��
���������껿��
������̣�ι��ն� ��10�֥֡�åѡ�
���ش����륤�������ꥢ����֡�Louis Auriacombe��
�����ա��ȥ����롼������ɸ����ġ�Orchestre de Chambre de Toulouse��
�����Ǹ���EMI
- �������
��Jean Gilles��1668-1705���ե��
�������͡��������ڥǥ����֥�������
�������ڥǥ����֥������פι������
�֥������ϥե�������Х��å����ڤκ�ʲȡ���ʩ��α�ޤä���齡�����ڲȤȤ��Ƴ�ư�����������ν����ʤ���Ǥ⡢�Ȥ�櫓�ԥ쥯��������ϥ���ɥ졦����ץ�Τ�Τ��¤�ǡ��ե����Ǥ�ޤ���줿��
����ά��37�Фˤʤä���������ޤ��Ƥ��뤬�����ͽ�����ƥ쥯������䤤���Ĥ��Υ�ƥåȤ�ʬ���Τ���˺�ʤ��Ƥ��롣�����ν����ʤϡ�Ʊ����ʩ�пȤΥ���ץ��Ϥ��ᡢƱ�����¿���β��ڲȤ����ܤ�椤����
������Υ쥯�������15�Υ�ƥåȡ������Ĥ��Ρԥ���ߥ��ΰ��Ρդϡ��Ⱦ��Ԥ��Τ���ʬ�ȹ羧�˲Τ�����ʬ�Ȥθ��ؤˤ�äơ���������륿�����ͼ���������Ƥ��ꡢ�ְ㤤�ʤ������ꥢ���Х��å����ڤ���αƶ����Ƥ��롣��������륿�����ͼ��ˤ��쥯���������ϡ����Ǥ˥���ץ�ΡԻ�ԤΤ���Υߥ��ʡդˤ⸫�Ф���뤬������κ���ϥ���ץ�ۤɥݥ�ե��˥å��Ǥʤ���������θ���������Ū�����Ѥ���Ƥ���Ȥ��ä�������⸫�������롣
������Υ쥯������ϡ��ѥ��ͭ̾�ʥ����롦���ԥ�ƥ奨��ˤ�ä�15���餵�줿�ۤ�����⡼��ݡ����ɲ������˥����1�����륤15�����Ǥ���դ��줿���ԥ������륤��������ϻ修����ǡ����뤬��ä�Ĺ�������Ƥ���줿�ʤ�С��ְ㤤�ʤ��ɥ�����θ�Ǥ�����Ф줿�Ǥ������ȽҤ٤Ƥ��롣��
��Messe des morts (Requiem)��
���ش���Philippe Herreweghe
�����Ǹ���ARCHIV PRODUKTION
- ������ե���åס���⡼
��Jean-Philippe Rameau��1683-1764���ե��
����������ʸ�β�ī���ե���ڤ���ɽ�������κ�ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥�����ե���åס���⡼��
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
������ե���åס���⡼������ɤ�ʿ����������ʽ����ˢ�ι�
�֥�����ե���åס���⡼�ϡ�����ʸ�β�ī���ե���ڤ���ɽ�������κ�ʲȤǤ���
����ά�˥�⡼�ϵ���ڲȤȤ��ƶ���������������äŤ���Ȥ����������줿���Ӥ�Ĥ��ޤ�������
��ʲȤȤ��ƤϤȤ��˥��ڥ�ȥ��������ʥ�����Х��ˤΥ�����Ǹ���٤���Τ�����ޤ�������ά��
������ɤ���Ȥ����ʤϡ��֥��å��å����áפȤ����ܤ��Ĥ���������Ū�˰��äƤ����Τǡ�
�����Ʋ���Ū���ƤΤ�����ʤǤϤ���ޤ������줬����ʤ�����Ū��ɸ�겻�ڤ˽���餺��
�ե�ʤ�ǤϤλ���ȥ����ץ��ɤ��Ƥ������ǡ����äǤ���
���ΰ�̣�������ץ�����⡼�����Υե������֥��ڤϡ��ɥӥ�å�������������
�ԥ��β��ڤ����Ȥʤ�ޤ�������
�إ����롦����������ʽ���
����Ͽ�ʡ�
����������ˤ�륯�������ʽ��裱�ȶ�(Premier concert)���
�����������ꥫ��(La Coulicam)
�������������(La Livri)
����������������(Le Vezinet)
����������ˤ�륯�������ʽ��裴�ȶ�(Quatrième concert)���
���������ѥ�ȥޥ���ʥѥ�ȥߥ��(La pantomime)
���������ڤϤ��ߤʤ�����٤��̵��θ��(L'indiscrète)
���������顦��⡼(La Rameau)
����������ˤ�륯�������ʽ��裵�ȶ�(Cinquièe concert)���
���������顦�ե��륯��(La Forquerey)
���������顦����ԡʥ���ԥ���(La Cupis)
���������顦�ޥ�(La Marais)
����������ˤ�륯�������ʽ��裲�ȶ�(Deuxième concert)���
����������ܥ��(La Laborde)
���������֥���(La Boucon)
����������������ȡʤ��뤵����Ρ�(L'agaçante)
����������̥��å�Ⅰ&Ⅱ��Menuet Ⅰ&Ⅱ)
����������ˤ�륯�������ʽ��裳�ȶ�(Troisième concert)���
���������顦�ݥץ�˥�����(La Pouplinière)
���������ⵤ(La timide)
������������֥��Ⅱ(Tambourin Ⅱ en rondeau)
�����Ǹ���PAVANE RECORDS
��MEISTERWERKE DES FRANZÖSISCHEN BAROCK��
����Ͽ�ʡ�
�������������ʽ��裵�ȶʡʥ�ĹĴ�ˤ��
�������������ץȤν� (L'Egyptienne)
����������̥��å�1,2 (Menuet Ⅰ&Ⅱ)
�������������ʽ��裳�ȶʡʥ�ûĴ�ˤ��
���������䤵�����ʤ��ʥ���ɡ���(Les tendres plaintes )
�������������ʽ��裲�ȶʡʥ�ûĴ�ˤ��
������������ɡ������ˤ�른������ (Gigue en rondeau)
��������������̥��Υꥴ�ɥ� (Rigaudon de Dardanus)
����(�ʾ塢Jean-Philippe Rameau)
�����Ǹ���MUSICA MUNDI
- ���祻�ա��ܥ��ɡ��ܥ���ƥ���
��Joseph Bodin de Boismortier��1689-1755���ե��
�������ե�������Х��å����ڤκǽ�Υե���ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥��祻�ա��ܥ��ɡ��ܥ���ƥ�����
�������ڥǥ����֥��祻�ա��ܥ��ɡ��ܥ���ƥ����פι������
�֥��祼�ա��ܥ��ɡ��ܥ���ƥ����ϥե�������Х��å����ڤκ�ʲȡ���ڶʡ������������ڥ顦�Х졢���ڶʤ�������������������������Ǥʤ����߸�Ԥʤ��ǡ�������Ϻ�Ȥ��ν��ǤΤߤˤ�ä����פ�Ω�Ƥ뤳�ȤΤǤ������ǽ�Υե��κ�ʲȤǤ��롣��⡼���¤�ǡ�����������β��ڼ�̣��ô�ä���ͤǤ��롣
������
���ܥ���ƥ����ϡ������ꥢ�Υ��������ȷ�����ò������ǽ�Υե�ͺ�ʲȤǤ��롣�ե�����Ρ����ճڴ������Ǥ��붨�նʤ�ǽ�˺�ʤ����Τ�ܥ���ƥ����Ǥ���ʡԥ��������롢����������ޤ��ϥХå���Τ���ζ��նʡ�1729ǯ�ˡ��ܥ���ƥ����ϡ��ե롼�ȤΤ���˿�¿���κ��ʤ��ʤ��������Ǥʤ����ե롼�ȶ�§�ܤ⼹ɮ�����ʤ��������ߤϻ���ˡ����ߤ⤷�Ф��б��դ������ʤϡ��ԥ���ʡ��ǡʤޤ��ϥ���ե��ˡ�����2�� Deuxieme Serenade Ou Simphonie�դǤ��롣��
��MEISTERWERKE DES FRANZÖSISCHEN BAROCK��
����Ͽ�ʡ�
����Orchestersonate a-moll op.34,6
����(���ꡧOrchestral sonata in A minor)
����(ʩ�ꡧSonate pour cordes en la mineur)
�����Ǹ���MUSICA MUNDI
- ������ޥ���륯�졼��
��Jean-Marie Leclair��1697-1764���ե��
������18�����ե�ˤ�����������������դε�
�������͡��������ڥǥ����֥�����ޥ���륯�졼���
�������ڥǥ����֥�����ޥ���륯�졼��פι������
�֥�����ޥ���륯�졼��ϡ��Х��å����ڤκ�ʲȤǡ�18�����ե�ˤ�����������������դεǤ��롣�ե��٥륮�����������������ɤ��ϻϼԤȸ�������Ƥ��롣
�����������Τ���ο����Υ��ʥ��䶨�նʤΤۤ����ȥꥪ�����ʥ��䡢�ե롼�Ȥ������㲻�Τ���Υ��ʥ���䤷�Ƥ��롣��
��MEISTERWERKE DES FRANZÖSISCHEN BAROCK��
����Ͽ�ʡ�
����Orchestersonate Nr.3 d-moll
����(���ꡧOrchestral sonata in D minor)
����(ʩ�ꡧSonate pour cordes en ré mineur)
�����Ǹ���MUSICA MUNDI
- �ǥ����ȥ�ҡ��֥����ƥա���
��Dieterich Buxtehude��1637��-1707���ɥ��ġ�
�������ɥ��ĥХ��å����ڤΥ��륬���ռ�
�������͡��������ڥǥ����֥ǥ����ȥ�ҡ��֥����ƥա��ǡ�
�������ڥǥ����֥ǥ����ȥ�ҡ��֥����ƥա��ǡפι������
�֥ǥ����ȥ�ҡ��֥����ƥա��Ǥϡ�17�������̥ɥ��Ĥ���ӥХ�ȳ�����ϰ衢�ץ����������ɽ�����ʲȡ����륬�˥��ȤǤ��롣����ά��
1667ǯ11��5������塼�٥å������ޥꥢ����Υ��륬�˥��ȤǤ���ե��ġ��ȥ������������1668ǯ4��11�����֥����ƥա��Ǥ����θ�Ǥ�����Ф���롣3�ʸ��ס�54���ȥåפ����������ޥꥢ������祪�륬����ô������⤯��Ʊ����Υ��륬�˥��Ȥ��̥ɥ��Ĥβ��ڲȤˤȤäƺǤ���פ��ϰ̤�1�ĤȤ���Ƥ���������ά��
�֥����ƥա��Ǥ����ڲȤȤ��Ƥμ��Ӥ�ȯ�������Τϡ�����ά�˥����٥�ȥॸ������ͼ�٤β���:Abendmusik�ˤˤ����ƤǤ��롣����ά�˥����٥�ȥॸ����������̵���Ȥ������Ȥ⤢�äƹ⤤�͵�������֥����ƥա��Ǥ�̾���ϥ�塼�٥å���Ķ���ƹ��ޤ롣�����٥�ȥॸ�����ηк�Ū��ô�Ϸ褷�Ʒڤ���ΤǤϤʤ��ä��������¤ʥ֥����ƥա��ǤϻԤ�ͭ�ϼԤ�����Ȼٱ�����뤳�Ȥ��Ǥ�������Ĺ�ڡ��������ϥ����ҡ��ƥ��ɥ�ץդϡ���ǯ��˴���֥����ƥա��Ǥ����ŷ��Τ褦��ƴ���ͽ�������Ƥ��줿��������ޥꥢ����ˤ����륢���٥�ȥॸ�������礤���Ϥ�Ԥ������פȸ�äƤ��롣��
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥ɥ��Ĥκ�ʲȥ֥����ƥա��Ǥϡ�����������Ⱦ���̤Υϥ��Իԥ�塼�٥å��dz������Ƥ��ޤ������Ȥ�櫓����ά�ˡ�ͼ�٤β��ڡפϡ������Υɥ��ĤǤ��äȤ�ͭ̾�ʲ��ڥ�������ȤǤ���������ά��
������ХåϤ⡢�֥����ƥա��Ǥα��դ�ʹ������ˡ�������ɥ��Ĥ�������ι�Ԥ�
��塼�٥å���Į�ˤ�äƤޤ���ޤ�����������ά����ХåϤϡ��֥����ƥա��Ǥˤ��ä��괶�㤷�Ƥ��ޤ���
���Υ���奿�åȤΥ��륬�˥��Ȥο�̳��ͥ��������Ф��ơ��Τ������̤ܶ����ȤˤʤäƤ��ޤä��ΤǤ�����
��BUXTEHODE vol.2��
����Ͽ�ʡ�
����[A��]
�������նʤȥա�������ûĴ (Prélude et fugue en mi mineur) ��
�������㥳��̡���ûĴ? (Chaconne en ut mineur) ��
�������顼����褿������衢��ʤ����
��������(Komm, heiliger Geist, Herr Gott)��BuxWV.199
�������նʤȥա�������ûĴ (Prélude et fugue en mi mineur) ��
����[B��]
����Toccata en fa majeur ��ˮ������
�������顼���ŷ�ˤޤ��ޤ���������
��������(Vater unser in Himmelreich)��BuxWV.219
�������նʤȥա�������ûĴ (Prélude et fugue en mi mineur) ��
�������������Ƥ����ʤ����ᡢˮ��Ͽ�¬������ΤǤ���
�����륬��ALKMAAR (������ Saint-Laurent����)
�����Ǹ���harmonia mundi
��BUXTEHUDE vol.3��
����Ͽ�ʡ�
����[A��]
�������նʡ��ա����ȥ��㥳��� ��ĹĴ?
��������(Prélude, fugue et chaconne en ut majeur) ��
�������顼��֤������Ӥ����Ƥ뤳����
��������(Der Tag, der ist so freudenreich)��BuxWV.182
����Fugue en ut majeur ��ˮ������
����Toccata et fugue en fa majeur ��ˮ������
�� ���顼���ŷ�ˤޤ��ޤ���������
��������(Vater unser in Himmelreich)��BuxWV.219
�������顼��ּ祤���������ꥹ�Ȥ衢���Ϥ��Ȥ��Ȥ��Τ��
��������(Herr Jesu Christ, ich weiss gar Wohl)��BuxWV.193
����[B��]
�����ѥå����ꥢ����ûĴ? (Passacaille en ré mineur) ��
�����ȶʡּ�˴��դ��������? (Partita:��Danket dem Herrn��) ��
����Prélude et fugue en ré mineur ��ˮ������
�������顼��֤郎��Ȥ��褿�졢�ȿ��λҸ�ꤿ�⤦
��������(Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn)��BuxWV.201
����Prélude et fugue en ré majeur ��ˮ������
�������������Ƥ����ʤ����ᡢˮ��Ͽ�¬������ΤǤ���
�����륬��ALTENBRUCH (�ɥ��� Saint-Nicolas����?)
�����Ǹ���harmonia mundi
- ���奼�åڡ�����ƥ�����
��Giuseppe Tartini��1692-1770�������ꥢ��
�����������ꥢ���Х��å�����κ�ʲȤˤ��ơ�������������̾��
�������͡��������ڥǥ����֥��奼�åڡ�����ƥ����ˡ�
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥����������ε�ˡ��Ű��Ū�˳��������������εݤ�Ĺ�������ꡢ
����ˡ�ʤɤο�������ˡ���ϻϤ����ꤷ�ޤ����������������̤Ǥ�ͥ�줿�Ż��Ƥ��ޤ�����
��Υ�����������̾�ͷݡʥ�����ƥ��������ˤ�䴸�ʤ�ȯ�������Τ������Ρ㰭��Υȥ���Ǥ�����
��SIX SONATES POUR VIOLON, VIOLONCELLE & CLAVECIN
����le Trille du Diable��
����Ͽ�ʡ�
����[A��]
����SONATE EN LA MAJEUR OP.1 No1
����SONATE EN SOL MINEUR OP.1 No10
����[B��]
����SONATE EN FA MAJEUR OP.1 No12
����SONATE EN LA MINEUR OP.2 No7
����SONATE EN DO MAJEUR OP.2 No6
����SONATE EN SOL MIEUR "LE TRILL DU DIABLE"�ʰ���Υȥ���
�����Ǹ���ERATO
- ���㡼�륺��������������
��Charles Avison��1709-1770��
�������Х��å������ŵ�ɤˤ����ƤΥ����ꥹ�κ�ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥��㡼�륺���������������
��12 CONGERTI GROSSI after DOMENICO SCARLATTI��
��ˮ�ꡧ�ɥ�˥����������åƥ��Υ��ʥ��˴�Ť�12�ι��ն��ն�
�����Ǹ���PHILIPS
- �����륯���ե���åס��ƥ�ޥ�
��Georg Philipp Telemann��1681-1767��
����������Х��å����ڤ���ɽ����ɥ��Ĥκ�ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥����륯���ե���åס��ƥ�ޥ��
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥ƥ�ޥ�ϡ���ХåϤ�إ�ǥ��Ʊ�����˥ɥ��Ĥ˳����������ڲȤǤ�����������̾�ϥХåϡ��إ�ǥ�Τ��ǡ����衼���åѤˤʤ�ҤӤ��Ƥ��ޤ��������٤Ƥο͡���ʿ�פ�̥��Ū�˸�꤫���뤽�ο��ͷݤȥ����ӥ������������ƥ�ޥ�����ΤǤ��ꡢ�Ҥ����罰Ū�ʿ͵��������̩�ʤΤǤ�������ʸ�ؤˤ��������Ѽ���������Τ褦��¸�ߤȤ����С���������Ǥ��礦����
���δɸ����ȶ�����β��ڡ��ϡ�����ά�˰���Ʋ������ե�դ��ν��ʤȡ�����Ū��ɽ�����Ķ�ĤγھϤ���Ǥ��Ƥ��ޤ�������ά�����ھϤ���ϥ�֥륯��Ĭ���������Ǥϡ��ʤθ�Ⱦ����Ⱦ�β����Τ������η����Ѥ��륤���ꥹ�Υ�����ʤι���ˡ�����Ѥ��ơ�Ĭ��������������Ƥޤ������Ƥ椯ͭ�ͤ桼��饹�ˤ������Ƥ��ޤ���
�㥿���ե���ॸ�������������Сֿ���ڡפǤ�������ά�������ϲ�����²�ν�ŵ�Ѳ��ڤȤ��Ʊ��դ��줿�褦�Ǥ�������ά��
����Ū�ˤ⽼�¤��Ƥ��ơ������ι��ա����դΤ������Υƥ��˥å���ե��ư��������ͥ�줿���ʤǤ�������ά��
�����Τβ�����²�ΤҤ��ߤˤʤ�äơ����ζʤΥ쥳���ɤ�ʹ���ʤ��顢�ڤ���������Τ�춽���Ȼפ��ޤ�����
��DIE OUVERTÜREN DER TAFELMUSIK��
��ˮ�ꡧ�����ե���ॸ����
�����Ǹ���TELEFUNKEN
�����ա�Concherto Amsterdam
���ش���Frans Brüggen
��10 Triosonaten��
��ˮ�ꡧ�ȥꥪ�����ʥ�
�����Ǹ���TELEFUNKEN
�����ա�Kees Boeke�ʥХ��å��ե롼�ȡ�
�������� Alice Harnoncourt�ʥ�����������
�������� Wouter Möller�ʥ�������
�������� Bob van Asperen�ʥ�����Х���
��WASSERMUSIK »HAMBUGER EBB UND FLUHT«��
��ˮ�ꡧ���β��ڡ֥ϥ�֥륯��Ĭ��������
�����Ǹ���ARCHIV
��Doppelkonzerte��Double Concertos��
�����Ǹ���TELEFUNKEN
��TRUMPET CONCERTOS��
�����ꡧ�ȥ��ڥåȤȣ��ĤΥ����ܥ��Υ���������
�����Ǹ���PHILIPS
����Ͽ�ʡ�Concerto in D��D-dur��en Ré���ۤ�
- ���������ˡ��Хåƥ��������ڥ르�졼��
��Giovanni Battista Pergolesi��1710-1736��
��������ŵ�ɲ��ڤ��ͼ���Ǥ��������
�������͡��������ڥǥ����֥��������ˡ��Хåƥ��������ڥ르�졼����
�������ڥǥ����֥���Х�ˡ������åƥ��������ڥ르�졼���פι������
��1735ǯ�����ڥ�إ����ԥ����ǡ٤�����ޤǽ�餹�뤬���Ԥ��ʥݥ����롣���κ������ˤΤ�����Ĵ�����������������ڤκ�ʤ˼���Ȥ�褦�ˤʤꡢ1736ǯ�ˤϥʥݥ��٥ݥåĥ���������ե�����������ƻ�������ܤ˰ܤ롣�ʥݥ�߽���²�ν��ޤ���ᤷ�ߤ����쵳����Cavalieri della Virgine dei Dolori�פ���Ѿ����줿�إ������Хȡ��ޡ��ƥ� Stabat Mater�١��ᤷ�ߤ��������;�Ϥ�ʤäƽ夲���ޤ�ʤ�©�������ä���26�Фμ㤵�Ǥ��ä���
�����������ϸ¤�줿��ΤǤ��ä�������͵����徺�������η�̤Ȥ��Ƶ�����̤˽в�뤳�Ȥˤ�ʤä���¿���κ��ʤ����ä���κ�ʤȤ��졢���κ����1939��42ǯ�ΡҺ��������Ӥˤޤǵڤ�Ǥ��롣
20������Ⱦ�ˤϥ������ꡦ���ȥ�����������ڥ르�졼���κ��ʤ��椫����ʤ����ӡ��²��ʤɤ��ѹ���ä��ƥХ쥨���ڡ֥ץ���ͥ��פȤ����������Ѥ��ʤ����ڥ르�졼���κ��ʤ�����ŵ������볫����𤲤����Ȥ϶�̣��������
�֥Х��å�̾��̾��100�סʳ���ã�ᡦ���ˤ�����
�֥��ڥ�Ȥ����ݽѤϡ�����������Ƭ���襤���ꥢ�ǽ�Ĵ��ȯŸ��ĤŤ�����Ȭ�����溢�ˤҤȤĤι⤤ĺ�����ۤ��夲�ޤ���������ά�ˤ������⥮�ꥷ�����äȤ���������ޤα�ͺ��ʪ��Ȥ��ä���������Ū�����ƤǤ��ä������ˡ��ʹ�Ū�ʴ���¸�ߴ��Ȥ�����Τ�����줬���Ǥ��ä��ΤǤ���������Ф��ơ��ڥ르�졼������ä����ڥ顦�֥åե��ʴ�η�ˤϡ�ʿ�ޤʻ�ο�ʪ�Υꥢ������贶���ߤ��Ȥ˲Τ��夲�ơ������ٻ������뤳�Ȥˤʤä��ΤǤ�������
��STABAT MATER��
��ˮ�ꡧ�������Хȡ��ޡ��ƥ�
�����Ǹ���ARCHIV
- ����ȥ˥����롼���硦����������ǥ�
��Antonio Lucio Vivaldi��1678-1741�������ꥢ��
�����������ꥢ�Х��å����ڤˤ������ڲ��ڤ���Ȥˤ��ơ�
����������Ʊ���ˤ��θ�θ�ŵ�ɴ�ڲ��ڤδ���Ū¸��
�������͡��������ڥǥ����֥���ȥ˥�������������ǥ���
��GLORIA D-Dur / Koncertd-moll��
����Ͽ�ʡ�
�������쥯����ɥ����ޥ������
���������ܥ��ȹ��ն��ն�
����Gloria D-Dur�ʥ������ꥢ ��ĹĴ�ˡ�������������ǥ�
����Konzert d-moll�������쥵��ɥ����ޥ������
�����ա������쥹���ʡ����٥�ʡ����ޡ����������ȥ�
�����Ǹ���BASF
�ض��նʡ����ʣ��֡����֡�
�����ա����饦�ǥ��������⡼�͡��������ꥹ�ƥ����٥ͥƥ���
�����Ǹ���ERATO
��VIVALDI QUATTRO CONCERTI��
����Ͽ�ʡ�
����������������նʥ�ĹĴ�ֱΤ�����(Per eco)��RV.552,F.I-139,P.222
�������նʥ�ûĴRV.108,F.XII-11,P.77
����������������նʥ�ûĴ����(L'Inverno)��Op.8-4,RV.297,F.I-25,P.442
�����ե롼�ȡʥꥳ�������˶��նʥ�ûĴRV.441,F.VI-11,P.440
�����Ǹ���ERATO
�ض��ն�(VOL1)��
����Ͽ�ʡ�RV447 464 452 453 461 454
�����ա����饦�ǥ��������⡼�͡��������ꥹ�ƥ����٥ͥƥ���
�����Ǹ���ERATO
�ض��ն�(VOL2)��
����Ͽ�ʡ�RV 64 456 451��455 448 465
�����ա����饦�ǥ��������⡼�͡��������ꥹ�ƥ����٥ͥƥ���
�����Ǹ���ERATO
�ض��ն� ���ʣ����顦�����ȥ��������˥���Ĵ�¤���ˡ�
�����ա������ǥߡ�������ȥߥ塼���å�
�����Ǹ����ѡ��ǥå�
������
��VIVALDI-BACH�����¢���Ƥ��ޤ�
���顦�����ȥ��������˥���12�ʤ��椫�顢J.S.�ХåϤˤ���Զʤ��줿�ʤ��Ͽ��
����Ͽ�ʡ�
��������Υ�����Х��Τ���ζ��նʥ�ûĴBWV.1065��
�������̢����ʤ�A.����������ǥ�����3-10��
�������ն��裷�֥�ĹĴBWV.978��̢����ʤ�A.����������ǥ��κ���3-3��
��VIVALDI��
����Ͽ�ʡ�
����������������նʥ�ûĴOp.6-1,RV.324
����������������ն��ѥ�ĹĴOp.6-2,RV.259
����������������նʥ�ûĴOp.6-3,RV.318
����������������նʥ�ĹĴOp.6-4,RV.216
����������������նʥ�ûĴOp.6-5,RV.280
����������������նʥ�ûĴOp.6-6,RV.239
���������ܥ����ն��ѥ�ĹĴOp.7-1,RV.465
����������������նʥ�ĹĴOp.7-2,RV.188
����������������նʥ�ûĴOp.7-3,RV.326
����������������նʥ�ûĴOp.7-4,RV.354
����������������նʥ�ĹĴOp.7-5,RV.285a
����������������ն��ѥ�ĹĴOp.7-6,RV.374
���������ܥ����ն��ѥ�ĹĴOp.7-7,RV.464
����������������նʥ�ĹĴOp.7-8,RV.299
���������̢��ХåϤ�cemb���նʥ�ĹĴBWV973���Զʤ������ʡ�
����������������ն��ѥ�ĹĴOp.7-9,RV.373
����������������նʥ�ĹĴOp.7-10,RV.294a
����������������նʥ�ĹĴOp.7-11,RV.208a
����������������նʥ�ĹĴOp.7-12,RV.214
�����ա����⡼�͡��٥ͥƥ���
�����Ǹ���ERATO
��6 BASSOON CONCERTOS��FAGOTTOCONZERTE��
����Ͽ�ʡ�
�����ե����åȶ��նʥ�ĹĴRV.485
�����ե����åȶ��ն��ѥ�ĹĴRV.503
�����ե����åȶ��ն��ѥ�ĹĴRV.483
�����ե����åȶ��նʥ�ûĴRV.497
�����ե����åȶ��նʥ�ĹĴRV.473
�����ե����åȶ��նʥ�ĹĴRV.492
�����ա��ॸ�������ġ��ե����åȡ����饦�����ȥ����ͥޥ�
�����Ǹ����ե���åץ�
�إ���������ǥ������ն�������
�����ա����ॸ��������
�����Ǹ����ե���åץ�
����Ͽ�ʡ�
�������3�֡�֥顦�����ȥ��������˥�����Ĵ�¤θ��ۡ�
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ĹĴOp.3-1,RV.549,F.IV-7,P.146
���������նʥ�ûĴOp.3-2,RV.578,F.IV-8,P.326
������������������նʥ�ĹĴOp.3-3,RV.310,F.I-173,P.96
�����������̢��ХåϤ����ն��裷�֥�ĹĴBWV.978���Զʤ������ʡ��͢���¢
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ûĴOp.3-4,RV.550,F.I-174,P.97
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ĹĴOp.3-5,RV.519,F.I-175,P.212
������������������նʥ�ûĴOp.3-6,RV.356,F.I-176,P.1
���������նʥ�ĹĴOp.3-7,RV.567,F.IV-9,P.249
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ûĴOp.3-8,RV.522,F.I-177,P.2
�����������̢��ХåϤ����륬���նʥ�ûĴBWV593���Զʤ������ʡ�
������������������նʥ�ĹĴOp.3-9,RV.230,F.I-178,P.147
�����������̢��ХåϤ�������Х����նʥ�ĹĴBWV972���Զʤ������ʡ�
���������նʥ�ûĴOp.3-10,RV.580,F.IV-10,P.148
�����������̢��ХåϤ�������Х����նʥ�ûĴBWV1065���Զʤ������ʡ͢���¢
���������նʥ�ûĴOp.3-11,RV.565,F.IV-11,P.250
�����������̢��ХåϤ����륬���նʥ�ûĴBWV596���Զʤ������ʡ�
������������������նʥ�ĹĴOp.3-12,RV.265,F.I-179,P.240
�����������̢��ХåϤ�������Х����նʥ�ĹĴBWV976���Զʤ������ʡ�
�������4�֡��LA STRAVAGANZA��
������������������ն��ѥ�ĹĴOp.4-1,RV.383a,F.I-180,P.327
������������������նʥ�ûĴOp.4-2,RV.279,F.I-181,P.98
������������������նʥ�ĹĴOp.4-3,RV.301,F.I-182,P.99
������������������նʥ�ûĴOp.4-4,RV.357,F.I-183,P.3
������������������նʥ�ĹĴOp.4-5,RV.347,F.I-184,P.213
������������������նʥ�ûĴOp.4-6,RV.316a,F.I-185,P.328
������������������նʥ�ĹĴOp.4-7,RV.185,F.I-186,P.4
������������������նʥ�ûĴOp.4-8,RV.249,F.I-187,P.253
������������������նʥ�ĹĴOp.4-9,RV.284,F.I-188,P.251
������������������նʥ�ûĴOp.4-10,RV.196,F.I-189,P.413
������������������նʥ�ĹĴOp.4-11,RV.204,F.I-190,P.149
������������������նʥ�ĹĴOp.4-12,RV.298,F.I-191,P.100
�������ʥ�����������ռԡ�FELIX AYO [Nr.1-12]��WALTER GALLOZZI [Nr.7]��
�������8�֡��IL CIMENTO DELL'ARMONIA E DELL'INVENZIONE��
�������ȥ���٥��λ�ߡ�
������������������նʥ�ĹĴ�ֽ�(La Primavera)��
����������Op.8-1,RV.269,F.I-22,P.241
������������������նʥ�ûĴ�ֲ�(L'Estate)��Op.8-2,RV.315,F.I-23,P.336
������������������նʥ�ĹĴ�ֽ�(L'Autunno)��Op.8-3,RV.293,F.I-24,P.257
������������������նʥ�ûĴ����(L'Inverno)��Op.8-4,RV.297,F.I-25,P.442
������������������ն��ѥ�ĹĴ�ֳ�����(La Tempesta di mare)��
����������Op.8-5,RV.253,F.I-26,P.415
������������������նʥ�ĹĴ�ִ��(Il Piacere)��Op.8-6,RV.180,F.I-27,P.7
������������������նʥ�ûĴOp.8-7,RV.242,F.I-28,P.258
������������������նʥ�ûĴOp.8-8,RV.332,F.I-16,P.337
������������������նʥ�ûĴOp.8-9,RV.454,F.VII-1,P.259
�����������̢������ܥ����ն�RV.236��Ʊ���
������������������ն��ѥ�ĹĴ�ּ���(La caccia)��Op.8-10,RV.362,F.I-29,P.338
������������������նʥ�ĹĴOp.8-11,RV.210,F.I-30,P.153
������������������նʥ�ĹĴOp.8-12,RV.449,F.(I-31),P.8
�����������̢������ܥ����ն�RV.178��Ʊ���
�������ʥ�����������ռԡ�ROBERTO MICHELUCCI [Nr.1-4]��FELIX AYO [Nr.5-12]��
�������9�֡��LA CETRA��
������������������նʥ�ĹĴOp.9-1,RV.181a,F.I-47,P.9
������������������նʥ�ĹĴOp.9-2,RV.345,F.I-51,P.214
������������������նʥ�ûĴOp.9-3,RV.334,F.I-52,P.339
�����������̢������ܥ����ն�Op.11-6��Ʊ�ʡ�
������������������նʥ�ĹĴOp.9-4,RV.263a,F.I-48,P.242
������������������նʥ�ûĴOp.9-5,RV.358,F.I-53,P.10
������������������նʥ�ĹĴOp.9-6,RV.348,F.I-54,P.215
������������������ն��ѥ�ĹĴOp.9-7,RV.359,F.I-55,P.340
������������������նʥ�ûĴOp.9-8,RV.238,F.I-56,P.260
���������ĤΥ����������Τ���ζ��ն��ѥ�ĹĴOp.9-9,RV.530,F.I-57,P.341
������������������նʥ�ĹĴOp.9-10,RV.300,F.I-49,P.103
������������������նʥ�ûĴOp.9-11,RV.198a,F.I-58,P.416
������������������նʥ�ûĴOp.9-12,RV.391,F.I-50,P.154�̢����դ�Ĵ�����ѹ���
�������ʥ�����������ռԡ�FELIX AYO [Nr.1-12]��ANNA MARIA COTOGNI [Nr.9]��
�������10�֡��6 CONCERTI��(�ե롼�ȶ��նʡ�
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴ�ֳ������Op.10-1,RV.433,F.VI-12,P.261
�����������̢�����=RV.261��
�������ե롼�ȶ��նʥ�ûĴ����(La Notte)��Op.10-2,RV.439,F.VI-13,P.342
�����������̢�����=RV.104��
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴ�֤������Ҥ��Op.10-3,RV.428,F.VI-14,P.155i
�����������̢�����=RV.90��
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴOp.10-4,RV.435,F.VI-15,P.104
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴOp.10-5,RV.434,P.262
�����������̢�RV.442���裲�ھϤ��Ĵ������Ρ�
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴOp.10-6,RV.437,F.VI-16,P.105
�����������̢�����=RV.101��
�������ʥե롼���ռԡ�SEVERINO GAZZELLONI��
����5 CONCERTI ��CON TITOLI���
������������������նʥ�ûĴ�֤���������(Il Favorito)��
����������Op.11-2,RV.277,F.I-208,P.106
�������ʥ�����������ռԡ�ROBEROTO MICHELUCCI��
������������������նʥ�ĹĴ�ְ¤餮(Il riposo)��RV.270,F.I-4,P.248
�������ʥ�����������ռԡ�ANNA MARIA COTOGNI��
������������������նʥ�ûĴ�ֵ���(Il sospetto)��RV.199,F.I-2,P.419
�������ʥ�����������ռԡ�LUCIANO VICARI��
������������������նʥ�ĹĴ����(L'Inquetudine)��RV.234,F.I-10,P.208
�������ʥ�����������ռԡ�WALTER GALLOZZI��
������������������նʥ�ĹĴ������(L'Amoroso)��RV.271,F.I-127,P.246
�������ʥ�����������ռԡ�FELIX AYO��
����4 CONCERTI��
�����������ܥ����նʥ�ûĴRV.461,F.VII-5,P.42
�������ե����åȶ��նʥ�ûĴRV.484,F.VIII-6,P.137
�������ե롼�ȡʥꥳ�������˶��նʥ�ûĴRV.441,F.VI-11,P.440
�������ե롼�ȶ��նʥ�ĹĴRV.427,F.VI-3,P.203
����4 CONCERTI��
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ûĴRV.523,F.I-61,P.28
�������ʥ�����������ռԡ�FELIX AYO��ROBERTO MICHELUCCI��
���������ĤΥե롼�ȤΤ���ζ��նʥ�ĹĴRV.533,F.VI-2,P.76
���������ĤΥޥ�ɥ��Τ���ζ��նʥ�ĹĴRV.532,F.V-2,P.133
���������ĤΥ����ܥ��Τ���ζ��նʥ�ûĴRV.535,F.VII-9,P.302
����5 WERKE / 5 OEUVRES / 5 WORKS��
�����������������ȥ������Τ���ζ��ն��ѥ�ĹĴRV.547,F.IV-2,P.388
���������նʥ�ĹĴRV.564,F.IV-4,P.188
������������������նʥ�ĹĴ�ֱΤ�����(Per eco)��RV.552,F.I-139,P.222
���������ڤ������㲻�Τ���ζ��նʥ�ûĴ�֥ޥɥꥬ��������RV.129,F.XI-10,P.86
���������ڤ������㲻�Τ���ζ��ն��ѥ�ĹĴ�����ʤ���ˤ�(Al Santo Sepolcro)��
����������RV.130,F.XVI-2,P.441
����VERSCHIEDENE CONCERTI / CONCERTI DIVERS /
����������VARIOUS CONCERTOS��
���������ڤ������㲻�Τ���ζ��նʥ�ĹĴRV.158,F.XI-4,P.235
�����������������ȥ��륬��Τ���ζ��նʥ�ĹĴRV.542,F.XII-41,P.274
���������ڤ������㲻�Τ���ζ��նʥ�ûĴRV.153,F.XI-33,P.394
���������ĤΥ������Τ���ζ��նʥ�ûĴRV.531,F.III-2,P.411
���������ڤ������㲻�Τ���ζ��նʡʥ���ե��˥��˥�ûĴRV.134,F.XI-13,P.127
���������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ĹĴRV.551,F.I-34,P.278
���������������նʥ�ûĴRV.401,F.III-1,P.434
������������Electronically re-processed stereo���Ż�Ū�˺ƽ������줿���ƥ쥪����
�������ԥå����ʥե饦�ƥ����Ρ˶��նʥ�ûĴRV.445,F.VI-9,P.83
���������ĤΥȥ��ڥåȤΤ���ζ��նʥ�ĹĴRV.537,F.IX-1,P.75
��LE QUATTRO STAGIONI���ʺ���8�� �͵���
����Ͽ�ʡ�
������No.1 ��
������No.2 ��
������No.3 ��
������No.4 ��
���ش���Trevor Pinnoock�ʥȥ졼�С����ԥΥå���
���������Simon Standage
�����ա�The English Concert�ʥ���å��塦�����ȡ�
�����Ǹ���ARCHIV
��VIVALDI FOUR SEASONS���ʺ���8�� �͵� ���������ȥ��ס�
���ش����桼�����ݥޥ�ǥ�
����������������ա�Anshel Brusilow�ʥ����롦�֥饷������
�����ա�The Philadelphia Orchestra�ʥե���ǥ�ե����ɸ����ġ�
�����Ǹ���CBS SONY
��Vivaldi LE QUATTRO STAGIONI��
�����ա����ॸ��������
�������������FELIX AYO
�����Ǹ����ե���åץ�
- �����륯���ե�ɥ�ҡ��إ�ǥ�
��Georg Friedrich Händel��1685-1759���ɥ��Ģ������ꥹ��
�������ɥ������ޤ�Υ����ꥹ�˵���������ʲȤǡ�����ʥ���ȥꥪ��䤷��
�������͡��������ڥǥ����֥����륯���ե�ɥ�ҡ��إ�ǥ��
��WATER MUSIC��
��ˮ�ꡧ���β���
�����ա�COLLEGIUM AUREUM
�����Ǹ���harmonia mundi
����Ͽ�ʡ�
�����ֿ��β��ڡ��ȶʥ�ĹĴHWV.348���裱�֡�
�����ֿ��β��ڡ��ȶʥ�ĹĴHWV.349���裲�֡�
�����ֿ��β��ڡ��ȶʥ�ĹĴHWV.350���裳�֡�
��FIREWORKS MUSIC��
��ˮ�ꡧ���ܤβֲФβ���
�����ա�English Chamber Orchestra KARL RICHTER
�����Ǹ���ARCHIV
��Coronation Antherms��
��ˮ�ꡧ�״�������
�����ա�The English Concert
���ش���Trevor Pinnock
�����륬��Simon Preston
�����Ǹ���ARCHIV
��SÄMTLICHE SONATEN��
�����Ǹ���RCA
����Ͽ�ʡ�
�������ʥ�����ĹĴOp.1-7,HWV.365
�������ʥ�����ûĴHWV.374�ʥϥ졦���ʥ��裱�֡�
�������ʥ�����ûĴOp.1-8,HWV.366
�������ʥ�����ûĴOp.1-4,HWV.362
�������ʥ�����ĹĴOp.1-5,HWV.363b
�������ʥ�����ûĴHWV.375�ʥϥ졦���ʥ��裲�֡�
�������ʥ�����ûĴOp.1-2,HWV.360
�������ʥ�����ûĴHWV.376�ʥϥ졦���ʥ��裳�֡�
�������ʥ�����ûĴHWV.367a�ʥե��åĥ����ꥢ�ࡦ���ʥ��裳�֡�
�������ʥ��ѥ�ĹĴHWV.357(1709��10��)�ʥե��åĥ����ꥢ�ࡦ���ʥ��裱�֡���
�����������Х��å��ե롼�Ȥȥ����ܥ��ˤ��֤���������
�������ʥ�����ĹĴOp.1-11,HWV.369
����minuet e-moll�����ܺ���������ûĴ
����Andante h-moll�����ܺ���������ûĴ
��������̾���� ��ûĴ
��������̾���� ��ûĴ
����Allegro ��ĹĴ
��SAMTLICHE CONCERTI GROSSI OP.3+6��
��ˮ�ꡧ���ն��նʽ� ���ʣ�����
������������6�Ĥι��ն��նʽ� ����3�פȡ�12�ι��ն��նʽ� ����6�פ��Ͽ
�����ա�Academy of St.Martin-in-the-Fields
���ش���Neville Marriner
�����Ǹ���DECCA
��Ode for St. Cecilia's Day��
��ˮ�ꡧ�������ꥢ�ν����Τ�������
�����ա�CONCENTUS MUSICUS WIEN
���ش���Nikolaus Harnoncourt
�����ץ�Ρ�Felicity Palmer
���ƥΡ��롧Anthony Rolfe Johnson
�����Ǹ���TELEFUNKEN
��SÄMTLICHE ORGELKONZERTE��
�����ա�ORCHESTRE DE CHAMBRE JEAN-FRANÇOIS PAILLARD
���ش���Jean-François Paillard
�����륬��Marie-Claire Alain
�����Ǹ���ERATO
����Ͽ�ʡ�
�������륬���նʽ���4�֡���6�ʡ�
�������륬���նʽ���7�֡���6�ʡ�
�������륬���ն���13�֥�ĹĴ�֤��ä����ȥʥ�������סʸ��ꡧDer Kuckuck und die Nachtigall��
�������륬���ն���14�֥�ĹĴ
�������륬���ն���15�֥�ûĴ
�������륬���ն���16�֥�ĹĴ
��TAMERLANO���ʥ��ڥ��
��ˮ�ꡧ�ηࡡ�����顼��
�����ա�JACOBS��ELWES��VAN DER SLUIS��MALGOIRE
�����Ǹ���CBS MASTERWORKS
��ISRAEL IN EGYPT���ʥ���ȥꥪ��
��ˮ�ꡧ�����ץȤΥ����饨���
�����ա�CHOIR OF CHRIST CHURCH CATHEDRAL, OXFORD
�������� ENGLISH CHAMER ORCHESTRA
���ش���SIMON PRESTON
�����ץ�έ���ELIZABETH GALE
�����ץ�έ���LILIAN WATSON
������ȡ�JAMES BOWMAN
���ƥΡ��롧IAN PARTRIDGE
��������TOM McDONNELL
��������LAN WATT
�����Ǹ���argo
��SAUL���ʥ���ȥꥪ��
��ˮ�ꡧ������
�����ա�English Chamber Orchestra
���ش���CHARLES MACKERRAS
�����ʥ�����;Bass��Donald Mcintyre �ۤ�
�����Ǹ���ARCHIV
��JUDAS MACCABÄUS���ʥ���ȥꥪ��
��ˮ�ꡧ�ޥ��٥����Υ��
���ش���WOLFGANG GÖNNENWEIN
�����ʥ��;Tenor��PETER SCHREIER �ۤ�
�����Ǹ���harmonia mundi
��SAMSON���ʥ���ȥꥪ��
��ˮ�ꡧ���ॽ��
�����ա�Münchener Bach-Orchester
���ش���KARL RICHTER
�������饹��Münchener Bach-Char
�������ॽ����Alexander Young�ʥƥΡ���� �ۤ�
�����Ǹ���ARCHIV
��Alexander's Feast���ʥ���ȥꥪ��
��ˮ�ꡧ���쥰��������ζ±�
�����Ǹ���TELEFUNKEN
��MESSIAH���ʥ���ȥꥪ�ˢ��Ѹ���
��ˮ�ꡧ�����
�����ա�London Phiharmonic Orchestra
�������饹��John alldis Choir
���ش���KARL RICHTER
�����Ǹ���Grammophon
��DER MESSIAS���ʥ���ȥꥪ�ˢ��ɥ��ĸ���
��ˮ�ꡧ�����
�����ա�Münchener Bach-Orchester
�������饹��Münchener Bach-Char
���ش���Karl Richter
�����Ǹ���Grammophon
- ��ϥ��Х��ƥ����Хå�
��Johann Sebastian Bach��1685-1750���ɥ��ġ�
���������β��ڻ˾�Ǥ�äȤ����ʲ��ڲȤ��ʤ�����˸����Ȳ��ڤ����
�������͡��������ڥǥ����֥�ϥ��Х��ƥ����Хåϡ�
�֥Хåϡסʥ������ɡ��졼�ޥ����ˤ�����
����������ȥ���ե��˥��ι�
�֥�����������Τ���ν��ޤΥ���������Ƚ��ޤΥ���ե��˥����ʤ����Ȥ��ˤϡ��ХåϤϤޤ�
������Ȥ������ȡ��Ĥޤ�Ҷ��������Ȥ��˥�����إ���ե�ǥޥ�Τ���˳ؽ���ˡ���Ω����
���Ȥ��ɵᤷ���Τ��ä������������ե��˥��ȤϤ��ξ�硢�������Υ���������Τ��ȡ���
����ά�ˤ����㥤���������Ȣ㥷��ե��˥���ϡ���ά�˵�ǽŪ����ˡ�Ⱥ�ʤؤμ�ۤɤ��Ȥ�
���פ����褦�Ȥ��롢��������Ū��ߤȹͤ��Ƥ褤����
��THE BRANDENBURG CONCERTOS��
��ˮ�ꡧ�֥��ǥ�֥륯���ն�
�����Ǹ���LONDON ffrr
�����ա�Karl Münchinger��Stuttgart Chamber Orchestra
�������ʥ����롦�ߥ��إ��ȥ���ĥåȥ���ȼ���ɸ����ġ�
����Ͽ�ʡ�
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裱�֥�ĹĴ BWV.1046
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裱�֥�ĹĴ BWV.1046a
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裲�֥�ĹĴ BWV.1047
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裳�֥�ĹĴ BWV.1048
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裴�֥�ĹĴ BWV.1049
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裵�֥�ĹĴ BWV.1050
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裵�֥�ĹĴ BWV.1050a
�����֥��ǥ�֥륯���ն��裶���ѥ�ĹĴ BWV.1051
��Brandenburgische Konzerte Nr.1-6��
��ˮ�ꡧ�֥��ǥ륯���ն�
�����Ǹ���TELEFUNKEN
���ش���Karl Richter und sein Kammerorchester
�����������ܸ����������롦��ҥ�������μ���ɸ����ġ�
����Ͽ�ʡ��ʾ�ά��
�֥��ǥ�֥륯���ն�
�����ζʤϥХåϤΤ��μ�κ��������η��Ǥ��ꡢ���ĥ��������ȡ������å��ȸƤФ�����ζʤ���Ǥ��äȤ�ͥ�줿���ʤǤ��äơ��إ�ǥ롢�������η��⤳��ˤ�����ڤФʤ��Ȥ���롣���ߤޤǤ˸��椵��Ƥ���Ȥ����ˤ��ȡ����ζʤ������Ѥ����Ƥ����������αƶ�������Ƥ��뤳�ȡ������Х�ǥ��Τ����ζ��նʤλ��ļ�����Ǥ������졢�����Хåϼ��Ȥιͤ��ˤ������äƺ���Ѥ����Ѥ��Ƥ������Ȥ��Τ��Ǥ���ȹͤ����Ƥ��롣
�������Ǥϡ��¤ϡ��֥��ǥ�֥륯���նʤȤ�����Τ�����Ω�����ü�ʶʽ��Ȥ��ƤޤȤ�뤿��˽줿�ΤǤϤʤ�������˿�¿�����ä����նʤ��椫�顢�������������ӽФ��줿��Τ��ä����Ȥ��Τ��Ƥ��롣
�����Τ褦�ʶ��նʤ��椫�飶�ʤ����֥��ǥ�֥륯��������β���©�ҡ��ޥ륯���顼�ե�����ն���˥��ꥹ�ƥ����롼�ȥ����ҤΥ��������ȥ�Τ���ˡ����ӽФ��줿�ɤΤǤ��롣
���ڴ�κ������Ȥ߹�碌�����ܤ��Ƥߤ�ȡ����Ĥζ��նʤ������줾�츹�ڴ�β��������ۤ����Ĥζ��նʤ������Ƥ��뤳�Ȥ��狼�롣���Τ��Ȥ��顢���Σ��Ĥζ��նʤĤΥ��롼�פ�ʬ�ह�뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���裱�Υ��롼�פ��裱�֥�ĹĴ���裲�֤�ĹĴ�ǡ��ȥ��ڥåȤȼ��ĥۥ��ȥ����ܥ��ε������������Τ���ζ��նʤ�ޤࡣ�裲�Υ��롼�פ��裴�֥�ĹĴ���裵�֥�ĹĴ�ǡ��裱�Υ��롼�פ���䤵������������ͭ����ڴ�������Ѥ����Ƥ��롣�裳�Υ��롼�פϻĤ���裳�֥�ĹĴ���裶���ѥ�ĹĴ�ǡ����ڴ�Τߤˤ���Ť��ǹ����ܤʶ��նʤȤʤäƤ��롣
���ޤ����裲�֡��裴�֡��裵�֤ϥإ�ǥ�䥳���꤬���夲�����������ȡ������å��ʹ��ն��նʡˤη�����ȤäƤ��롣
�裳�֥�ĹĴ
�����ζʤϡ����������ȡ������å��Ȥ��ƤϷ��ˤ�ǡ��������ȹ������ζ��̤��ʤ����Ƴڴ郎��������ξ�ԤƤʤꤢ�äơ�ȿ��Ū���̤�Ф����Ȥ����ä��Τ����������ھϤ���ʤꡢ���δ֤˥եꥮ�����ߤ�ʤ����Ĥ��²�����Ƥ��롣���ߤǤϤ�����ʬ�����̤˽Ƥ���Ȥ�����դ���뤬�����뤤�Ϥ��ξ��¨���˥��ǥ�ĥ����դ���Τ�������ԤΰտޤǤϤʤ����Ȥΰո��⤢�롣
�裴�֥�ĹĴ
�����ζʤι������ϡ������դ������㲻�ڴ�ǡ��ɸ��ڤϲä��ʤ����裲�ھϤǤϡ������������ΤȤ��ƹ���������Ω���뤬���裱���裳�ھϤǤϥ���������Ǥ��������Τǡ�������������նʤ˶ᤤ��
�裵�֥�ĹĴ
�����ζ��նʤˤ����������Х��ϡ����������㲻�Ȥ����Ѥ���������������餫�˥��������ȳڴ�Ȥ����Ѥ����롣���Τ��ᡢ������ʬ�ϥ�����Х����նʤȤߤʤ����Ȥ��Ǥ����ʼ�ϥХ��å�Ū�ǤϤʤ䤫�Ǥ��롣���Τ��ᤳ�ζʤϡ������ˤ��ƣ�����Ǥ�͵��Τ����ΤȤʤäƤ��롣
��Musikalisches Opfer��
�����ꡧ���ڤ��������
�����Ǹ���TELEFUNKEN
����Ͽ�ʡ�Ein musikalisches Opfer BWV.1079
�����ա��˥��饦���������Υ��ȡ�Nikolaus Harnoncourt�ˤۤ�
��������Concentus musicus Wien
��OUVERTÜREN��
����Ͽ�ʡ�
�����ɸ����ȶ��裲�֥�ûĴ BWV.1067
�����ɸ����ȶ��裳�֥�ĹĴ BWV.1068
����
�����ա�Münchener Bach-Orchestrer�ʥߥ��إХåϥ��������ȥ��
���ش���Karl Richter�ʥ����롦��ҥ�����
�����Ǹ���ARCHIV
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ס����ˤ�����
�ɸ����ȶ��裲
��BACH SUITE H-MOLL / TRIPELKONZERT A-MOLL��
����Ͽ�ʡ�
����Suite Nr. 2 h-moll BWV1067
�����ʴɸ����ȶ��裲�֥�ûĴ BWV.1067��
����Tripelkonzert a-moll BWV1044
�����ʥե롼�ȡ������������ȥ�����Х��Τ���ζ��նʥ�ûĴBWV.1044��
���������裱�����ھϤ����նʤȥա�������ûĴBWV.894���顢
���������裲�ھϤϥ��륬��Τ���Υ��ʥ��裳�֥�ûĴBWV.527������Զ�
���������裲�ھϤϥ⡼�ĥ���Ȥ����ڻ����դΤ�����Զʤ��Ƥ��롣��K404a-5)
���ե롼�ȡ�Peter-Lukas Graf
�������������José Luis García
��������Х���Jörg Ewald Dähler
���ش���Peter-Lukas Graf
�����ա�English Chamber Orchestra�ʥ����ꥹ����ɸ����ġ�
�����Ǹ���Clovers
��J.S.BACH��3 CONCERTI��
����Ͽ�ʡ�
������Concert for Flute, Violin, Harpsichord, Strings and Basso Continuo in A minor, BWV1044
������"Triple Concerto"
�������ʥե롼�ȡ������������ȥ�����Х��Τ���ζ��նʥ�ûĴBWV.1044��
������Concerto for Oboe, Violin, Strings and Basso continuo c-moll, nach BWV1060
�������ʥ����������ȥ����ܥ��Τ���ζ��նʡ���
������Concerto for Oboe d'amore, Strings and Basso Continuo in A Major, after BWV1055
�������ʥ����ܥ������⡼�춨�նʡ���
���ش���Trevor Pinnock�ʥȥ�С����ԥΥå���
�����ա�The English Consort
��BACH VIOLIN CONCERTOS NOS1&2 / DOUBLE VIOLIN CONCERTO��
����Ͽ�ʡ�
����������������ն��裱�֥�ûĴBWV.1041
����������������ն��裲�֥�ĹĴBWV.1042
�������ĤΥ����������Τ���ζ��նʥ�ûĴBWV.1043
���ش���Louis Auriacombe�ʥ륤���������ꥢ����֡�
�����ա�Toulouse Symphony Orchestra
�����Ǹ���EVEREST
��Johann Sebastian & Carl Philipp Emanuel BACH Cembaloconzerte��
����Ͽ�ʡ�
����������Х����ն��裱�֥�ûĴBWV.1052
�������ʢ����ʤϥ�����������ն�
�����������裱�����ھϤϥ�������146�֤֡��餢�ޤ��ζ����Ф�(Wir mussen durch viel Trubsal in das Reich Gottes eingehen*)��BWV.146�ˡ��裳�ھϤϥ�������188�֤֡��Ϥ郎�����(Ich habe meine Zuversicht)��BWV.188�ν��ʤ�ž��
����������Х����նʥ�ûĴWq.23
���ش���������Х���Gustav Leonhardt�ʥ������ա��쥪��ϥ�ȡ�
�����Ǹ���RCA
��JOHANN SEBASTIAN BACH / Goldberg-Variationen��
����Ͽ�ʡ�
���� Goldberg-Variationen BWV.988
���� �ʥ���ȥ٥륯���նʥ�ĹĴ��
���ش���Trevor Pinnock�ʥȥ�С����ԥΥ��å���
�����Ǹ���ARCHIV
��SZIGETI J.S.BACH 6 SONATAS & PARTITAS FOR VIOLIN ALINE��
����Ͽ�ʡ�
����̵ȼ�ե�����������ʥ��裱�֥�ûĴ BWV.1001
����̵ȼ�ե���������ѥ�ƥ������裱�֥�ûĴ BWV.1002
����̵ȼ�ե�����������ʥ��裲�֥�ûĴ BWV.1003
����̵ȼ�ե���������ѥ�ƥ������裲�֥�ûĴ BWV.1004
����̵ȼ�ե�����������ʥ��裳�֥�ĹĴ BWV.1005
����̵ȼ�ե���������ѥ�ƥ������裳�֥�ĹĴ BWV.1006
�������������Joseph Szigeti�ʥ��祻�ա������åƥ���
�����Ǹ���VANGUARD
�֥Хåϡסʥ������ɡ��졼�ޥ����ˤ�����
�֤����Υѥ�ƥ������ȥ��ʥ��ϡ��ɼԤ������ȶʤ�����ؤ�Ϣ���ɤ����Ȥˤʤ롣
���������٤ϡ���������������ʤ˸����ʤ��ä�����¿����Ū���ʤ������ɽ���椿���ǡ�
�����ΧŪ�ǡ��ޤ���긷�ʤ��ȶʤȤʤ롣
�ѥ�ƥ������ˤĤ��Ƥϡ��ե��Ū�ͼ��ˤ�ä������μ�̣�˰ܤ��줿�����ꥢ��ʲȤ�����
�ּ��⥽�ʥ��פ��ط�����ȹͤ��ƤϤ����ʤ������������������Ƥ��äݤ����ʥ��ˤĤ��Ƥϡ�
��Ĥδ˽��ھϤ���ĤεھϤ���ġֶ��ʥ��פ��ͤ����ʤ�����������
������פ���ˡ����륫������������ȥ�����ޥꡦ�륯�졼��Ȥ��֤���ط���
���ꤵ��̤��Ȥ������ȤʤΤ�������
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ס����ˤ�����
̵ȼ�ե�����������ȶ��裲�֥�ûĴ�ι�
�֤��ä����ܤΥ����������ݡݡ�̵ȼ�աפ�̾�Τ褦�˥�����Х��Ȥ��ԥ��Τ�ȼ�դ�
���ä�������ޤ���ݡݤ����ǡ��������̩�٤Τ������֤�Ҥ����Ƥ椯�Ȥ������Ȥ�
�����ؤ�ʤ��ȤǤ��͡�
�����������������ϽŲ���ˡ�Ȥ��äơ������Ĥ��β���Ʊ�����դ��뤳�ȤϤǤ��ޤ�����
����ˤ��Ƥ��������ǥ��ڴ�Ǥ�������������ˡ���������Τդ���ɽ�����ǽ�Ȥ������ΤǤ����顢
�ХåϤȤ�����ʲȤϥ�������β��ڤ��Ȥ��虜��ޤ���
���������֥ѥ�ƥ������ˤϤ���ޤ������ʥ����ʤǤϡ��ա����ޤDZ��դ����Ƥ��ޤ���
�ͤ��Ƥ�ߤƤ������������륬���ԥ��ΤǤϤʤ����������������ܤǥա�����Ҥ�����ΤǤ��衣
����������ò���Ƥ��ޤ��Ф���ʤΤǤ�����
��BACH / Flötensonaten��
����Ͽ�ʡ�
����Sonata (��) in b minor, BWV.1030
�����ʥե롼�Ȥȥ�����Х��Τ���Υ��ʥ� ��ûĴ �裱�֡�
����Sonata (��) in E, BWV.1035
�����ʥե롼�Ȥ������㲻�Τ���Υ��ʥ� ��ĹĴ �裳�֡�
����Sonata (��) in A, BWV.1032
�����ʥե롼�Ȥȥ�����Х��Τ���Υ��ʥ� ��ĹĴ �裳�֡�
����Sonata (��) in d minor, BWV.1034
�����ʥե롼�Ȥ������㲻�Τ���Υ��ʥ� ��ûĴ �裲�֡�
����Concerto in d minor(Fragment)
���ե롼�ȡ�Frans Brüggen�ʣ��������ܡ�
��������Х���Gustav Leonhardt�����ʡ�
���裱�����������Sigiswald Kuijken
���裱�ӥ��顧Wieland Kuijken
�����Ǹ���RCA
�֥Хåϡסʥ������ɡ��졼�ޥ����ˤ�����
�֢㥯�顼�������ȥե롼�ȤΤ���Υ��ʥ����HP����������BWV1030��1032�ˤˤ����ƥХåϤϡ�
�ե롼�Ȥ�����������Ρ����Ѥ�׳ڴ�ȸ��ʤ�������ˡ��ѵݳڴ���Ф���ΤȤ��ʤ��褦��
Ǯ�äݤ�ɽ�����ᤷ����
��ե롼�Ȥ����աʿ������㲻�Τ���Υ��ʥ����HP����������BWV1033��1035�ˤϷ���Ū�ˤ�
�����ꥢ�դ��Τ�Τǡ��ȶʤդ��γƳھϤ����ˤϥ�̥��åȤ��뤤�ϥ����ꥢ���Τβ����ǰ��������졢
�ޤ����ˤϡ֥����ꥢ�����ʥ��פμ�ˡ������Ť����롣�����������ζʤ�����Ūõ��ϡ�
�ޤ��ʤ�Ȥ�������������Ƥ��뤳�Ȥ���������
��VIVALDI-BACH��
����Ͽ�ʡ�
�������նʥ�ûĴ Op.3-10,RV.580,F.IV-10,P.148
�����ʢ�����������ǥ���ʡ��ХåϤ�BWV1065���Զʡ�
����������������նʥ�ĹĴOp.3-3,RV.310,F.I-173,P.96
�����ʢ�����������ǥ���ʡ��ХåϤ�BWV.978���Զʡ�
��������Υ�����Х��Τ���ζ��ն� ��ûĴ BWV.1065
�����ʢ��ХåϤ�����������ǥ���Op.3-10���Զʡ�
�������ն��裷�֥�ĹĴBWV.978
�����ʢ��ХåϤ�����������ǥ���Op.3-3���Զʡ�
�����Ǹ���Acharlin
�֥Хåϡסʥ������ɡ��졼�ޥ����ˤ�����
��¾�κ�ʲȤ����ˤ�ȤŤ���ϻ�ζ��նʢ��BWV972��987��
�֥������ޥ�ǥԥ���ǥ��𤷤ơ����ڴ�Τ���˽줿�����ꥢ�ζ��նʤ���Ƥ���Ĥ��ɤ�
����������������ǡ������Υ��顼�ӥ������ؤ��ݰƤ��Զʤ�������褷�褦�Ȥ��ơ�
�����Ǯ���ˤȤ��Ȥ����
��Ϥޤ����ʤγ����ƺ٤˸�Ƥ���������������Ĥ��ǿ������а�ˡŪ���̤��Ѥ��ơ����Ƥ�
�����褦�ˤ������Ȥ����������μ�ˡ�ϥ���������ǥ��䥢��å���ɥ���٥ͥǥåȡ��ޥ�����å���
���ʤ�ͭ���Ǥ�������Ǥʤ����ơ���ޥ�䥶�����������ޥ�Υ�ϥ��륽���ȸ��κ��ʤ�
�礷�Ƥ�ͭ���ʤ��Ȥ��狼�äƤ���������ά��
������ζ��նʤϡ��Ƕ�ˤ�����ޤ�˺����Ƥ������������������ˤϸ���Ū�Ǥ������ꡢ
���ä���ñĴ�ʤ�ΤǤʤ������κ��ʤ˿ͤӤȤ��ܤ�����������Τϡ������Ƕ�Τ��ȤǤ����ʤ�����
��HP�����������֤����Ƕ�פϤ����ܤ���ɮ���줿������1970ǯ���塩�ˤΤ��ȤǤ���������
��GOULD plays BACH / Italian Concerto Préludes,Fugues,etc... /
��GLENN GOULD��
����Ͽ�ʡ�
���������ꥢ���նʥ�ĹĴ BWV.971
���������ꥹ�ȶ��裳�֥�ûĴ BWV.808
�����ե���ȶ��裵�֥�ĹĴ BWV.816
���������ꥹ�ȶ��裲�֥�ûĴ BWV.807
���������նʥ�ĹĴ BWV.933
���������նʥ�ûĴ BWV.934
�������նʤȥա����裱�֥�ĹĴ BWV.846
�������նʤȥա����裲�֥�ûĴ BWV.847
�����ե���ȶ��裳�֥�ûĴ BWV.814
�����ե���ȶ��裶�֥�ĹĴ BWV.817
�����ѥ�ƥ������裱���ѥ�ĹĴ BWV.825
��������ȥ٥륯���նʥ�ĹĴ BWV.988
���ԥ��Ρ�Glenn Gould
�����Ǹ���CBS RECORDS / MASTERWORKS
�֥Х��å�̾��̾�ף������סʳ���ã�ס����ˤ�����
�����ꥢ���նʤι�
�֤��ζʤˡ㶨�նʡ��̾��������Ƥ��ޤ��������������ȥ�Ĥ��κ��ʤǤϤʤ���������Х������
���դ�����ΤǤ�������ά��
�ɤ����Ƥ�ԥ��ΤΤ�ΤȤ�������˾�Ǥ����顢�֥��ǥ뤫�����ä��פ����äƥ�����ɤϤ�����
�Ǥ��礦�����ɤ������Ρ㥤���ꥢ���նʡ�ϰ��Υѥ�ɥå����Τ�������Ω���Ƥ�����ʤʤΤǤ����顢
�ռ�ˤȤäƥѥ�ɥå�����Ű����Ȥ����Τ�ҤȤĤΤ椭�����⤷��ޤ���
�֥Хåϡסʥ������ɡ��졼�ޥ����ˤ�����
�ե���ȶʤι�
�֤����ϻ�ʤ���ʤ��ȶʤϡ��Ϥ�������նʤ�����̤Ȥ������¤ˤ�ä��ưפ˼��̤���롣
��ʤ����ǤǤ��Ƥ���ΤǤ��롣
���ʤ�������������ˤ��Ǥ�ή�Ԥ��Ƥ�������Ū�ʻ��Ĥ���ʡ�
����Ҥ����뤤�㥢��ޥ�ɢ䡢�����Ҥˤ���ȯ�ʢ㥯�����Ȣ䡢����ҤΤ��䤫��
�㥵��Х�ɢ��ޤࡣ�����γڶʤȺǸ�㥸������Τ������ˡ����������ή�Ԥ��Ƥ���
�ե����ʡ��Ĥޤ��֡����㥬�����åȢ���̥��åȢ䡢�Ȥ��ˤϥե�դ��Υ����롢
����˥롼�����������ե�θŤ����ʡ��ˡʥ롼�줹��Ȥϥ쥬���ȤǤĤʤ��Ȥ�����̣��
�ʤɤ��������줿������ά��
�ǽ�λ��Ĥ�ñĴ�ǡ��Ĥ��λ��Ĥ�ĹĴ�Ȥʤ롣�Ϥ���λͤĤ��ȶʤ�ϻ�ھϤ���ʤ��������
����֤Υ�̥��åȤ���ʤȹͤ��롣�ˡ��Ǹ����Ĥϼ��Ĥ�Ȭ�ĤγھϤ���ʤäƤ��롣��
��BACH Two and Three Part Inventions��
����Ͽ�ʡ�
���������������裱�֥�ĹĴBWV.772
��������ե��˥��裱�֥�ĹĴBWV.787
���������������裲�֥�ûĴBWV.773
��������ե��˥��裲�֥�ûĴBWV.788
���������������裵���ѥ�ĹĴBWV.776
��������ե��˥��裵���ѥ�ĹĴBWV.791
����������������14���ѥ�ĹĴBWV.785
��������ե��˥���14���ѥ�ĹĴBWV.800
����������������11�֥�ûĴBWV.782
��������ե��˥���11�֥�ûĴBWV.797
����������������10�֥�ĹĴBWV.781
��������ե��˥���10�֥�ĹĴBWV.796
����������������15�֥�ûĴBWV.786
��������ե��˥���15�֥�ûĴBWV.801
���������������裷�֥�ûĴBWV.778
��������ե��˥��裷�֥�ûĴBWV.793
���������������裶�֥�ĹĴBWV.777
��������ե��˥��裶�֥�ĹĴBWV.792
����������������13�֥�ûĴBWV.784
��������ե��˥���13�֥�ûĴBWV.799
����������������12�֥�ĹĴBWV.783
��������ե��˥���12�֥�ĹĴBWV.798
���������������裳�֥�ĹĴBWV.774
��������ե��˥��裳�֥�ĹĴBWV.789
���������������裴�֥�ûĴBWV.775
��������ե��˥��裴�֥�ûĴBWV.790
���������������裸�֥�ĹĴBWV.779
��������ե��˥��裸�֥�ĹĴBWV.794
���������������裹�֥�ûĴBWV.780
��������ե��˥��裹�֥�ûĴBWV.795
���ԥ��Ρ�Glenn Gould
�����Ǹ���CBS RECORDS / MASTERWORKS
��Sonaten für Violine und Cembalo��
�ʱ��ꡧSonatas for Violin and Harpsichord��
��ʩ�ꡧSonates pour violon et clavecin��
�����Ǹ���ARCHIV
����Ͽ�ʡ�
����Sonate Nr.1 h-moll / in B minor / en si mineur
����Sonate Nr.2 A-dur / in A major / en la majeur
����Sonate Nr.3 E-dur / in E major / en mi majeur
����Sonate Nr.4 c-moll / in C minor / en ut mineur
����Sonate Nr.5 f-moll / in F minor / en fa mineur
����Sonate Nr.6 G-dur / in G major / en sol majeur
������BWV.1014��1019��
�����ռԡ�
�����Х��å��Х������Eduard Melkus
�������������Huguette Dreyfus
��Weihnachts-Oratorium��(BWV.248)
�ʱ��ꡧCHRISTMAS ORATORIO��ˮ�ꡧ���ꥹ�ޥ�������ȥꥪ��
�����Ǹ���ARCHIV
�����ץ�Ρ�Gundula Janowitz
������ȡ�Christa Ludwig
���ƥΡ��롧Fritz Wunderlich
������Franz Crass
�������饹��Münchener Bach-Chor�ʥߥ��إХåϹ羧�ġ�
�����ա�Münchener Bach-Orchester�ʥߥ��إХåϴɸ����ġ�
���ش���Karl Richter�ʥ����롦��ҥ�����
��JOHANN SEBASTIAN BACH DAS ORGELWERK1��
�ʥХåϡ����륬�������������
�����إ�ࡼ�ȡ�������ҥ�ˤ��֥Хåϡ����륬����������פΣ����ܤ�Ͽ�����ʤȻפ��롣
�����Ǹ���ARCHIV
�����ա�Helmut Walcha�ʥإ�ࡼ�ȡ�������ҥ��
�����륬���륯�ޡ����������������祪�륬��
�����������ȥ饹�֡���Υ��ԥ����롦�롦����̶���С��ޥ��륬��
����Ͽ�ʡ�
����BWV.565/540/538/564
����BWV.542/572/562/582/537
����BWV.548/547/544/534
����BWV.552/541/546/543
����BWV.525/530/545/536/535
����BWV.526/527/528/529
����BWV.531/533/579/551/532/574/550
����BWV.588/589/590/539/578/1080
WikiPedia�֥إ�ࡼ�ȡ�������ҥ�פι������ѡ�
�إ�ࡼ�ȡ�������ҥ�κ���ζ��Ӥϡ��嵭���̤ꡢJ.S.�ХåϤΥ��륬����ʤ��Υ��Ͽ�������ƥ쥪Ͽ����2�٤ˤ錄��Ͽ���������ȤǤ��뤬��LP�쥳���ɤ䥹�ƥ쥪Ͽ�����о�ˤ�ꡢ�����ˤ�¿����ǯ�����䤷����
����ҡ��դǤϡ�����ά�˥ХåϤ������륬����ʤ�إ�ࡼ�ȡ�������ҥ�α��դˤ�äƥ쥳���ɲ����뤳�Ȥ�ײ褷�Ƥ��ꡢ����ά��Ͽ�����դ������ҥ㤬�ܤ�������Τ������ڥ�Υ���˥åȥ��������륬��Ǥ��롣1950ǯ����1952ǯ�ˤ����ơ��ХåϤΥ��륬����ʤΤۤȤ�ɤ�Ͽ�����줿�����֥Хåϡ����륬����������פ�1���ܤ�Ͽ���Ȥ����Τ��롣�� �����������ƥ쥪Ͽ���γ��Ϥˤ�ꡢ���Υ��륬��Ǥϡ������̤�����ˤ�ꡢϿ�������Ǥ��뤳�Ȥˤʤä���
���ˡ����Ф줿�Τϡ����륯�ޡ���������������Υ���˥åȥ��������륬���Ǥ��롣�����Ǥϡ��ɡ���ζ����������餷����ΤǤ��ꡢ����Ͽ�����줿��
�ХåϤΥ��륬�����������Ͽ���ײ褬���褷���Τϡ�1968ǯ�Τ��ȤǤ��롣�����Ǥϡ����ƥ쥪Ͽ����¿�������ƥ쥪Ͽ���ˤ���Ͽ����ɬ������ǧ���줿����ˡ����褵�줿�ȹͤ����롣����ά�˿�ˡ����ȥ饹�֡���Υ��ԥ����롦�롦����̶���Υ���С��ޥ��륬���������������С��ޥ�Υ��ꥸ�ʥ�Υ��ȥåפ϶Ϥ��ˤ����ĤäƤ��ʤ��ä����������ι������ַײ��ʤ�Ӥ˿���ɽ�˽��äơ������˽�������Ƥ�������Ǥ��롣
1971ǯ�ޤǤˡ��Ĥ�Υ��륬����ʤ�Ͽ�����졢��J.S.�Хåϡ����륬����������٤ϴ������������֥Хåϡ����륬����������פ�2���ܤ�Ͽ���Ȥ����Τ��롣��
������ҥ�α��դ������������ʵ���Ū���դȤߤʤ��줿��
��WikiPedia�ˤϡ֥���С��ޥ�Υ��륬��פȵ��ܤ���Ƥ��ޤ���������ϡ֥���С��ޥ��륬��פθ���Ǥ����Ƚ�Ǥ����������֥����ȤǤ��������ƷǺܤ��Ƥ��ޤ�����2013.5.2���ߡ�
������ŵ��
- ������ե������ޥǥ������⡼�ĥ����
��Wolfgang Amadeus Mozart��1756-1791����������������Ρ����ߤΥ������ȥꥢ��
��������ŵ�ɲ��ڤ���ɽ�Ǥ��ꡢ���������ŵ�ɻ���ΰ��
�������͡��������ڥǥ����֥�����ե������ޥǥ������⡼�ĥ���ȡ�
�ʸ���ʡ�
�������25�֡�26�֡�27����������θ����
�������29�֡�30�֡�34����������θ����
�������38�֥֡ץ�ϡס���35�֥֡ϥեʡ���
�������40�֡���39��
�������40�֡���41�֥֡���ԥ�����
�ʶ��նʡ�
�ե롼�ȶ��ն� �裱�� ��ĹĴ K.313 �� �����ܥ����ն� ��ĹĴ K.314
�����ܥ����նʥ�ĹĴK.314
�������� ��ĹĴ K.315
�ԥ��ζ��ն� ��19�� ��ĹĴ K.459 �� �ԥ��ζ��ն� ��20�� ��ûĴ K.466
�ʥߥ��ʡ�
�쥯������ ��ûĴ K.626
�ߥ��� ��ĹĴ ���״����ߥ���K.317
�ʤ���¾��
�����Ԥ������ղݡʥ������ڥ�˥�ĹĴ K.339
�ǥ�������ƥ����ȡʴ�ͷ�ʡ���17�� ��ĹĴ K.334
- �롼�ȥ����ҡ������١��ȡ�������
��Ludwig van Beethoven��1770��-1827����������������Ρ����ߤΥɥ��ġ�
���������饷�å����ڻ˾�ˤ�ư���ʺ�ʲȤΰ�ͤǤ��ꡢ
�������������������ŵ�ɻ���ΰ�ͤǤ⤢��
�������͡��������ڥǥ����֥롼�ɥ����ҡ������١��ȡ��������
����� �裳�� �ѥ�ĹĴ Op.55 �ֱ�ͺ(Eroica)��
�ʣ��̡˥ꥹ�ȡ������ �����նʡ�
�����ش���������إ�ࡦ�ե�ȥ����顼
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裴�� �ѥ�ĹĴ Op.60
�ʣ��̡˥��ꥪ������
�����ش���������إ�ࡦ�ե�ȥ����顼
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裵�� ��ûĴ Op.67 �ֱ�̿(Schicksal)��
�ʣ��̡˥��塼�٥�ȡ������ ��8�� ��ûĴ D.759��̤������
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裵�� ��ûĴ Op.67 �ֱ�̿(Schicksal)��
�ʣ��̡˥��塼�٥�ȡ������ ��8�� ��ûĴ D.759��̤������
�����ش�������ޥ�����
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裶�� ��ĹĴ Op.68 ���ı�(Pastorale)��
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裶�� ��ĹĴ Op.68 ���ı�(Pastorale)��
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
����� �裷�� ��ĹĴ Op.92
�����ش����ǥ����ǥ�������
�������ա��ץ�ϼ���ɸ�����
����� �裸�� ��ĹĴ Op.93
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裹�� ��ûĴ Op.125 �ֹ羧(Choral)��
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ����ġ����������ͧ����
����� �裹�� ��ûĴ Op.125 �ֹ羧(Choral)��
�ʣ��̡������ �裵�� ��ûĴ Op.67 �ֱ�̿(Schicksal)��
�����ش���������إ�ࡦ�ե�ȥ����顼
�������ա���������ե���ϡ���ˡ��ɸ����ġ��Х������Ƚ˺ףϣ�
���ʽ������ꥪ��쥪�Ρ��졦�ե��ǥꥪ����Ʋ������������
�����ش����������롦�ޥ륱�ӥå�
�������ա����롼�������
�ߥ��������˥����ߥ��� ��ĹĴ Op.123
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ����ġ����������ͧ����
�ԥ��ζ��ն� ��1�֡���5��
�����ԥ��Ρ�������إ�ࡦ�Хå��ϥ���
�����ش����ϥ�����ߥåȡᥤ�å��륷��ƥå�
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
�ԥ��Υ��ʥ� ��8�֥�ûĴOp.13�����ȡ�
�ԥ��Υ��ʥ� ��14�ֱť�ûĴOp.27-2�ַ����
�ԥ��Υ��ʥ� ��23�֥�ûĴOp.57��Ǯ���
�����ԥ��Ρ�������إ�ࡦ�����
�ԥ��Υ��ʥ� ��21�֥�ĹĴOp.53�֥��ȥ��奿�����
�ԥ��Υ��ʥ� ��23�֥�ûĴOp.57��Ǯ���
�����ԥ��Ρ�����ǥ��ߡ��롦�ۥ��ӥå�
�Х�������ն�
����������������ꥹ����ե��饹
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
�Х�����ʥ�����1�֡���10��
������������������å����ѡ���ޥ�
�����ԥ��Ρ�����ǥ����ߥ롦�����奱�ʡ���
�������ȥԥ��ΥΥʥ�����1�֡���5��
�������������ॹ�ƥ�����ա������ȥ��ݡ��ӥå�
�����ԥ��Ρ�������ȥ���ա���ҥƥ�
���ޥ���2�֥�ĹĴ Op.50
���������ߥ������ս�
�Х��ƥ� ��ûĴ�֥�����Τ���ˡ�
�����Хɥ��������������뽸
�������ޥ��ɲ���
�ᡥ������ޥ��ɲ���
- �ե��ġ��ڡ����������塼�٥��
��Franz Peter Schubert��1797-1828���������ȥꥢ��
��������ŵ�ɤ�����ޥ��ɤؤζ��Ϥ�Ū¸�ߡ��ֲζʤβ���
�������͡��������ڥǥ����֥ե��ġ����塼�٥�ȡ�
�������ڥǥ����֥ե��ġ����塼�٥�ȡפ����ѡ�
�֥��塼�٥�Ȥϰ���Ū�˥��ޥ��ɤ��Ȥ�������뤬�����β��ڡ������ϥ��������ŵ�ɤζ����ƶ����ˤ��ꡢ����ˡ������Ū�ʺ��ˡ���ŵ�ɤ�°���Ƥ��롣��²�Ҳ�κ�ʲȤ����̱�Ҳ�κ�ʲȤؤȤ������Ǥϥ��ޥ���Ū�Ǥ��ꡢ���ڻ�Ū�ˤϸ�ŵ�ɤȥ��ޥ��ɤζ��Ϥ�Ū���֤ˤ��뤬��ǯ��Ū�ˤϥ��塼�٥�Ȥΰ����ϥ١��ȡ�������θ�Ⱦ���ȤۤܽŤʤäƤ��ꡢ����Ū�ˤ����Υ١��ȡ������������˸�ŵŪ�Ǥ��롣
(��ά)
���塼�٥�Ȥ��Ĥ�������ե��ġ��衼���ա��ϥ��ɥ��ߥҥ㥨�롦�ϥ��ɥ⡼�ĥ���Ȥ�١��ȡ�������θ��ڻͽ��դ��²�DZ��դ���(��ά)���塼�٥�Ȥ�������������ǺǤ����ʲ��ڲȤǤ��ä��١��ȡ��������º�ɤ��Ƥ�����������ϰ��ݤ�ǰ�˶ᤤ��Τǡ��١��ȡ�������β��ڼ��Τ���������ǡֺ���¿���κ�ʲȤ˶��̤��Ƹ�������θ����פȤ��Ƥष���ɱƤ�����(��ά)
�ष�����塼�٥�Ȥ���������ʲȤϥ⡼�ĥ���ȤǤ��롣1816ǯ6��14�����⡼�ĥ���Ȥβ��ڤ�İ�������������ǥ��塼�٥�Ȥϥ⡼�ĥ���Ȥ�ʾ�̵���ۤɾ����Ƥ��롣
(��ά)
���塼�٥�Ȥϸ�κ�ʲȤ�¿���˱ƶ���Ϳ�����������Ĺ����ʡ٤�ȯ���������塼�ޥ�ϸ����˵ڤФ����ä˲ζʡ�����ʤˤ����ƥ��ǥ륹�����֥顼�ॹ���֥�å��ʡ���������ա���ҥ��ȡ�����ȥ饦�����ɥ����륶�����ʤɡ����塼�٥�Ȥβ��ڤ����ƶ����������ʲȤ�¿������
������裷�֡�̤������D759
�����ش���������إ�ࡦ�ե�ȥ٥顼
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����(B��)
�������ǥ륹�����Х�������ն�
���������ش���������إ�ࡦ�ե�ȥ٥顼
�����������ա��������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
���������Х�������桼�ǥ�����˥塼����
������裸�֥֡������졼�ȡ�D944
�����ش��������롦�ߥ��ҥ�
�����նʡ��ԥ��Τȸ���NO1 D471
�������������ѥ֥������륹
�����ԥ��Ρ������ȥߥ�
�����Х��������ʥ�����
�����նʡ��ԥ��Τȸ���NO2 D581
�������������ѥ֥��������륹
�����ԥ��Ρ��ߥ�������ա��ۥ륷��ե�����
�����Х�������쥯�������������ʥ�����
�ڶ��λ� �ԥ��������� D780
�����ԥ��Ρ�����ե졼�ȡ��֥��ǥ�
�ڶ��λ� �裳�� D780
�����ԥ��Ρ����֥ꥨ�ɡ������ɥ�
�ڶ��λ� �裲�� D780 �ѥ��륹���������뽸
¨���� �ԥ��������� D946
�����ԥ��Ρ�����ե졼�ȡ��֥��ǥ�
������
���塼�٥�ȸ���ʤ��ֹ��դ��ˤĤ��ƤϽ���ΰո���ʬ�����Ȥ������Ȼפ��ޤ������ܹƤǤϹ�ݥ��塼�٥�ȶ���ε����§�äƤ��ޤ���
�ʻ��͡������������ڥǥ����֥ե��ġ����塼�٥�ȡ��ݡ�����ʤ��ֹ��դ��ס�
�⡥������ޥ��ɲ���
- ��ϥͥ����֥顼�ॹ
��Johannes Brahms��1833-1897��
�������Хåϡ��١��ȡ�������ȶ��ˡ��ɥ��IJ��ڤˤ����뻰��֣¡פ��¤ӾΤ����
�������͡��������ڥǥ����֥�ϥͥ����֥顼�ॹ��
����� �裱�� ��ûĴ Op.68
�ʣ��̡���ؽ�ŵ����
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
����� �裲�� ��ĹĴ Op.73
�ʣ��̡���ؽ�ŵ����
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
����� �裳�� ��ĹĴ Op.90
�ʣ��̡��ϥ��ɥ�μ���ˤ�����ն� Op.56b
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裴�� ��ûĴ Op.98
�ʣ��̡��ϥ��ɥ�μ���ˤ�����ն� Op.56b
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
�ɥ��ġ��쥯������ Op.45
�����ش��������륰�������ƥ�
�������ա��������������
������������ն� ��ĹĴ Op.77
��������������������������������
�����ش����桼�������ޥ�ǥ���
�������ա��ե���ǥ�ե����������
�ԥ��ζ��ն� �裲�� �ѥ�ĹĴ Op.83
�����ԥ��Ρ����ɥ�����ɡ����ĥ���
�����ش����ϥ�������ե�����
�������ա����������Ω�η��ɸ�����
���� ��ĹĴ �ѥɥ��饹���������뽸
- �衼���ա�����ȥ֥�å��ʡ�
��Josef Anton Bruckner��1824-1896���������ȥꥢ��
�������������ȥꥢ�κ�ʲȤˤ��ơ�ͥ���ʥ��륬���ռ�
�������͡��������ڥǥ����֥���ȥ֥�å��ʡ���
�������ڥǥ����֥���ȥ֥�å��ʡ��פι�����ѡ�
�ָ�����ޥ��ɤ���Ǥ��ð������Ŧ����ɾ���Ȥ⾯�ʤ��ʤ�����Ĥϡ����ڥ��ʸ�ؤȤ������ξ��ʤ��Ǥ��ꡢ�������κ��ʤ˥��ڥ餬�Ĥ���Ƥ��ʤ����Ȥ䡢����ʡ��γڷ�֥�륭�塼��פ��Ф���̵����ˤ�ȤŤ��ä���ۡ���ά�ˤ���仡������ΤǤ��롣�⤦��Ĥϡ���ʽ�ˡ�ο��ǥ��륬���ռԤ�ȯ�ۤ������뤳�ȤǤ��롣
����ʤ���ˤ���Ǥϡ�Ĺ��ʱ��ջ��֤��פ�����ʤ���³�������ǡ����Ф��Хޡ��顼����Ӥ���롣�ޤ���Ʊ����κ�ʲȤ���Ǥϡ���ϥͥ����֥顼�ॹ����Ω����¸�ߤȤ��Ф���ª�����Ƥ��롣
������
�֥�å��ʡ��θ���ʤϲ��ơ��ä˥ɥ��ķ��Ǥ����ѿ͵����⤤�Τǡ��㤤�ش��Ԥ��Ѷ�Ū�˱��ղ�Ͽ���˼��夲�뤳�Ȥ�¿���������ǡ��Ť�Ͽ���ˤ�����̾�ش��Ԥˤ����դⷫ���֤�CD�Ȥ���ȯ�䤵�졢����İ����Ƥ��롣���ܤǤ⡢�֥�å��ʡ������Ԥ�¿�������յ���ˤ����Ū�ᤰ�ޤ�Ƥ��롣
������
�Ť��ϥ�����إ�ࡦ�ե�ȥ����顼��ϥ����ʥåѡ��ĥ֥å���ʤɤ�Ͽ�����Ƥ��ꡢ������CD�Ϻ��ʤ�����İ����Ƥ��롣�Ȥ�櫓��ŵ�ǽ��Ǹ������Ǥ���Ѥ�³�������ʥåѡ��ĥ֥å����Ͽ���ϡ�����λش��ԡ����������ȥ�ˤ������Ǥα��յ�Ͽ�Ȥ��Ƥ�Ťʤ�ΤǤ��롣
��
������裴�� �ѥ�ĹĴ�إ��ޥ�ƥ��å���
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
������裵�� �ѥ�ĹĴ
�����ʣ��̡˥���ʡ� ����˺�إˡ��٥�λشġ٤Σ����ܡؿ����β����٤���
��������Ⅰ���������ե�ȤΥ饤��ؤ�ι
��������Ⅱ���������ե�Ȥ������Կʶ�
�����ش����ϥ����ʥåѡ��ĥ֥å���
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��������
������裷�� ��ĹĴ
�����ʣ��̡˥���ʡ� ����˺�إˡ��٥�λشġ٤Σ����ܡؿ����β����٤���
�����������������ȥ饻�åȡ��ޥ����å���
��������Ⅰ���������ե�ȤΥ饤��ؤ�ι
��������Ⅱ�����ն� ���λ�
�����ش������������ե��ޥ����å�
�������ա����������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
������裸�� ��ûĴ
�����ش������åȡ��������ڥ顼
�������ա��˥塼���ե���ϡ���˥��ɸ�����
- �������ա��ޡ��顼
��Gustav Mahler, 1860-1911���������ȥꥢ����
�������֤䤬�ƻ�λ��夬���פȤ�̾����Ĥ������λ��200ǯ��Ф�
��������ͽ���ϸ��¤Τ�ΤȤʤä�
�������͡��������ڥǥ����֥������ա��ޡ��顼��
����� �裱�� ��ĹĴ �ֵ�͡�
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
����� �裱�� ��ĹĴ �ֵ�͡�
����� �裶�� ��ûĴ �����Ū��
����� �裹�� ��ĹĴ
�����ش�����ʡ��ɡ��С�������
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
����� �裲�� ��ûĴ �������
�������ץ�Ρ����ߥꥢ���������
��������ץ�Ρ��⡼��ե��쥹����
��������ȥ��ȡ��������ȥߥ����羧�Ģ�
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
����������ȥ��ȤȤϡ�����Ȥ���㤤����ǡ������κ��㲻��
����� �裳�� ��ûĴ
��������ץ�Ρ��ޡ�������ץȥ�
�����羧�������饫��ȥ��������羧�ġ��ȥ�ե�����졼�����ǯ�羧��
�����ش�����ʡ��ɡ��С�������
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
����� �裴�� ��ĹĴ ���礤�ʤ��Ӥؤλ��Ρ�
�������ץ�Ρ���ꡦ���쥹��
�����ش�����ʡ��ɡ��С�������
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
����� �裵�� �ť�ûĴ
�����ش����٥�ʥ�ȡ��ϥ���ƥ���
�������ա����ॹ�ƥ���ࡦ����ȥإܥ��ɸ�����
�ʣ��̡������ ��10�� �ť�ĹĴ ��̤����
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
����� �裷�� ��ûĴ ����βΡ�
�����ش�����ʡ��ɡ��С�������
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
����� �裸�� �ѥ�ĹĴ ����ͤθ���ʡ�
�������ץ�Ρ����ݡ����٥륯�����硼������˥㡼
��������ȡ��쥤�Υ��롿�ץ�������
�����ƥΡ��롧�ߥå���
�����Х�ȥ른�㡼��
�����Х����ޥå����䡼
�����ش�����ʡ��ɡ��С�������
�������ա�����ɥ�������
����� �����ϤβΡ�
�����ƥΡ��롧�ե�åġ�����������
��������ץ�Ρ���ɥ����å�
�����ش������åȡ��������ڥ顼
�������ա��˥塼�衼�����ե���ϡ���˥å�
- �ԥ硼�ȥ롦���ꥤ�������㥤���ե�����
��Ϫ�����ק�� ���ݧ�ڧ� ���ѧۧܧ�ӧ�ܧڧ�����ƥ�ʸ��ɽ��:Pyotr���뤤��Peter Ilyich Tchaikovsky��1840-1893����������
���������������ޥ��ɤξ�ħŪ¸��
�������͡��������ڥǥ����֥ԥ硼�ȥ롦���㥤���ե�������
����� �裱�� ��ûĴ Op.13 ���ߤ����θ��ۡ�
�����ش������ե��ˡ����������ȥ顼�Υ�
�������ա����������ȹ�Ω�������
����� �裲�� ��ûĴ Op.17 �־���������
�����ش������ե��ˡ����������ȥ顼�Υ�
�������ա����������ȹ�Ω�������
����� �裳�� ��ĹĴ Op.29 �֥ݡ����ɡ�
�����ش������ե��ˡ����������ȥ顼�Υ�
�������ա����������ȹ�Ω�������
����� �裴�� ��ûĴ Op.36
�����ش������硼��������
�������ա�����ɥ�������
����� �裵�� ��ûĴ Op.64
�ʣ��̡˥����ʡ����ڥ�إ륹���ȥ��ɥߥ��٤��
�����ش������ե��ˡ����������ȥ顼�Υ�
�������ա����������ȹ�Ω�������
����� �裶�� ��ûĴ Op.74 �����ȡ�
�����إ�٥�ȡ��ե��������ش�
�����٥��ե���ϡ���ˡ��������
����� Op.58 �֥ޥ�ե�åɡ�
��������ʥ��������������ȥ��������ش�
�����⥹���������������
�ԥ��ζ��ն� �裱�� �ѥ�ûĴ Op.23
�����ԥ��Ρ�������ȥ���ա���ҥƥ�
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��������
������������ն� ��ĹĴ Op.35
�ʣ��̡˥�������۶�
����������������ꥹ����ե��饹
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
������������ն� ��ĹĴ Op.35
��������������������åɡ��������ȥ��
�����ش����桼�������ޥ�ǥ���
�������ա��ե���ǥ�ե����ɸ�����
�Х쥨 ��̲��뿹�������� Op.66
�����ش�������ʥ��������������ȥ�������
�������ա��££ø������
�Х쥨����Ļ�θС�Op.20
�Х쥨��̲��뿹��������Op.66
�Х쥨�֤���߳��ͷ���Op.71
�����ش����桼�������ޥ�ǥ���
�������ա��ե���ǥ�ե����ɸ�����
- ����ȥ˥쥪�ݥ�ȡ��ɥ����륶����
��Antonin Leopold Dvořák, 1841-1904����������
������������ޥ��ɤ���ɽ�����ʲȤǤ��ꡢ���饷�å����ڻ����ؤο͵���ʲ�
�������͡��������ڥǥ����֥���ȥ˥ɥ����륶������
�������ڥǥ����֥���ȥ˥ɥ����륶�����פι�����ѡ�
�֥ɥ����륶�����ϡ�����ʡ����Х֥顼�ॹ�ɤ���Ω�����餫�Ȥʤä�����˳ؽ�����ޤ��Ƥ��롣1860ǯ���Ⱦ����ϥ���ʡ��β��ڤ˿��줷���ץ�Ϥǥ���ʡ��Υ��ڥ������餷�Ƥ����ɥ��ķ��ʥ��������ե��������ˤ��ˤ��̤ä���
1871ǯ�˺�ʤ������ڥ�ز��ͤ�ú�Ƥ�����1��ˤϡ�����ά�˥���ʡ��αƶ������餫�˸��Ƽ��롣�����������κ��ʤϼ��Ժ�ȸ��ʤ��졢����ޤ��뤳�ȤϤʤ��ä����ɥ����륶�����ϡ����Ρز��ͤ�ú�Ƥ�����1�������Ʊ�����ܤ˰ۤʤä����ڤ�Ĥ����ʥ�С������ڥ�˻�Ω�Ƥ��ز��ͤ�ú�Ƥ�����2��ʹߡ������˥���ʡ��αƶ�����æ���Ƥ�����
���������ɥ����륶�����κ�ǽ�ˤ�������ܤ����Τϡ�����ʡ������Ф��Ƥ����֥顼�ॹ�Ǥ��롣����ά����ϡ�����ά�˥���ʡ�����ؤ���ɥ�������֥顼�ॹ�����ܤ��빽���Ϥ�⤤�����Ƿ����������ʲȤǤ��ä���
�ȤϤ������ɥ����륶�����β��ڤ�Ȥ�櫓̥��Ū�ˤ��Ƥ���Τϡ����塼�٥�Ȥ��¤Ӿޤ���롢���οƤ��ߤ䤹������������ǥ����Ǥ��롣
��θ������9�֤���2�ھϤϡ����ܸ�βλ줬�Ĥ����ƾ��Ρֲ�ϩ�פȤ��ƿƤ��ޤ������Ǥʤ����ع���ǥѡ��Ȥʤɤν��Ȼ�����Τ餻�����ǥ����Ȥ��Ƥ�¿�����Ѥ���Ƥ��롣��
������裷�� ��ûĴ ����70 B.141
�����ش�����ե����롦�����٥�å�
�������ա��������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
������裸�� ��ĹĴ ����88 B.163
�����ش����������ĥ�ա��Υ��ޥ�
�������ա����������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
�����ʣ��̡˥�����ĥ������ץ�������� ����66
������裹�� ��ûĴ ����95 B.178�ֿ���������
�����ش����إ�٥�ȡ��ե�������
�������ա��٥��ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
������裹�� ��ûĴ ����95 B.178�ֿ���������
�����ش����֥롼�Ρ���륿��
�������ա�������ӥ��������
������裹�� ��ûĴ ����95 B.178�ֿ���������
�����ش�������롦���������
�������ա����������ե���ϡ���ˡ��ɸ�����
���ͻ���
�֥Х��å����ڡ�
�������ԡ�����ã��
�������Ǽҡ����̼Ҹ��忷��
���Х��å����ڤ������Ȥ��ƤȤƤ⤪������Ǥ�������ۤɳ���Ū�Ǥ�ʤ���ï�ˤǤ�狼��䤹��ʸ�ϤǤ���������Ƥ��������ɤߤ䤹�������Ȥ��äƾҲ𤵤�Ƥ���쥳���ɤϤɤ�⽨��ǡ������ܤ��ɤ�ХХ��å����ڤδ����μ�����̤����뤳�Ȥ��Ǥ���Ǥ��礦��
��Amazon.co.jp��
�֥Х��å�̾��̾��100��
�������ԡ�����ã��
�������Ǽҡ����̼�
���Х��å����ڤ�Ϥ���Ȥ��������ޤ��ޤʺ�ʲȤΤޤ��˶��ʽ�Ū����Ǥ������줾��κ�ʲȤ�����Ω�������ԥ����ɤ��顢��������ɽ��Τ��ȤޤDz��⤵��Ƥ��ꡢ�����ܤ��ɤ�ǥ쥳���ɤ�İ���Ƥ����дְ㤤�ʤ��Ǥ���������Ǥ���
��Amazon.co.jp��
�����Ǥ����ʲȡ��Хåϡ�
�������ԡ��������ɡ��졼�ޥ�
�������ԡ�Ź¼������������̦��
�������Ǽҡ�����Ƿͧ��
����ISBN��1373-220511-0777
��Amazon.co.jp��
�������ԤΥ������ɡ��졼�ޥ��Claude Lehmann�ˤϰ����Ѥ�ä�����ΥХåϸ���ȤǤ�����ϥ�塼�ޥ����Ť�����Ȥ���1921ǯ���ޤ�ΰ�ؼԤǡ������Τθ�����äƤ��ޤ����ܽ�Τۤ��ˤ⡢�ե�Ǥ�äȤ⸢�Ҥ����ѽ�֥ץ쥤�䡼�ɡפΡ㲻�ڤ���� Historie de la musique�����ΥХåϤ����ں��ʤ�������äƤ��뤳�ȤǤ⡢��Хåϸ���ʤȤ��ư�Ȥ�ʤ��Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ��������Ԥ��Ȥ�������
��̾�ʲ������� �裶�� ���նʾ��
�����Լԡ�����Ƿͧ��
����ȯ�Լԡ��ܹ�����
����ISBN��1373-010061-0777
�֥��饷�å��ǡ��������ۡ����ʴ�Ĺ�������ɰ���
�����ޤ��ޤʺ�ʲȤκ��ʤξܺ٤ʥǡ�����������Ƥ��ޤ���
�ʻ�����������ɽ��

WikiPedia����ϥ��Х��ƥ����ХåϤκ��ʰ�����
|